薬を飲んでいても、気分が晴れない…。
そんな時、「薬以外に自分でできることはないだろうか?」と、藁にもすがる思いで情報を探してしまうことがありますよね。
私も19年のうつ病経験の中で、同じ気持ちを抱えながら、いろいろなセルフケアを試してきました。
その中で出会ったのが、精神科医・藤川徳美先生の著書『うつ消しごはん』でした。
この記事では、私が『うつ消しごはん』を実践して感じたリアルな効果、そして、なぜ途中でやめてしまったのか。
その理由(費用や継続の難しさ、注意点)まで、一個人の体験談として包み隠さずお話しします。
これから試そうか迷っているあなたの、一つの判断材料になれば幸いです。
【体験談】『うつ消しごはん』を実践して感じた3つの変化
まず、私が「うつ消しごはん」から得られた「良い面」についてお話しします。
私の場合は、この食事法を始めたとき、うつ病の症状は比較的安定していました。
その上での体験談ですが、それでも確かに心と身体に良い変化を感じることができました。
(1) 気分の落ち込みがさらに安定した
もともと安定期だったこともありますが、日々の気分の波がより穏やかになったように感じました。
特に、理由もなくズーンと落ち込むような日が減ったのは、嬉しい変化でした。
(2) 無駄な食欲が自然と減った
以前は、お腹が空いていなくても、つい白米やうどんといった糖質中心の食事を多く摂りがちでした。
プロテインでタンパク質を摂るようになってから、過剰な食欲が自然と落ち着き、食事量が適正に近づいたように感じました。
(3) 身体が軽くなり、活動的になった
食事量が適正になった影響か、結果的に体重が少し落ちました。(あくまで私個人のケースです)
身体が軽くなると心も前向きになるのか、散歩や軽い運動をする気力も湧いてきて、良い循環が生まれているのを実感できました。
以上が、私がこの食事法から得られた「良い面」です。
ただ、良い変化を感じた一方で、続けるには現実的な壁もありました。
【本題】私が「うつ消しごはん」の実践をやめた3つのリアルな壁
良い変化を感じる一方で、この食事法を続けるにはいくつかの大きな「壁」がありました。
そして最終的に、私は実践を中断することになります。そのリアルな理由を3つ、お話しします。
壁(1)「継続のしにくさ」:サプリの大きさと味の現実
まず、シンプルに続けるのが大変でした。
-
サプリが飲みにくい
推奨されているサプリメントは海外製が多く、一粒がとても大きいんです。
喉につかえそうになることもあり、毎日いくつも飲むのは私にはかなりの負担でした。 -
プロテインが美味しくない
個人的な感想ですが、毎日飲むプロテインの味がどうしても好きになれませんでした。
最初は我慢できても、毎日となると食事が「楽しみ」ではなく「義務」に変わっていく感覚がありました。
壁(2)「経済的な負担」:月1万円超の出費という問題
そして、これが中断した最も決定的な理由です。
プロテインと数種類のサプリメントを毎日推奨量摂ると、月に1万~2万円ほどの費用がかかります。
体調が良くなることには代えられませんが、うつ病で思うように働けない状況の中、この出費を続けるのは非常に大きな負担でした。
「サプリ代のために、また頑張って働かないと…」と考えるようになり、本末転倒だと感じてしまったのです。
| 項目 | 月額費用の目安(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| プロテイン | 約5,000円 | 海外製1kgを1ヶ月で消費した場合 |
| ビタミンB群 | 約2,000円 | 海外製・高含有量タイプ |
| ビタミンC | 約2,000円 | 海外製・高含有量タイプ |
| ビタミンE | 約3,000円 | 海外製・高含有量タイプ |
| 合計 | 約12,000円 | 製品や購入量により変動します |
壁(3)「安全性への懸念」:主治医抜きで続ける孤立感
もう一つ、私の心にずっと引っかかっていたのが「安全性」の問題です。
「本当にこのまま続けて大丈夫だろうか?」
この不安を、主治医に相談できないまま一人で抱え続けることに、私は限界を感じてしまいました。
専門家である主治医の管理下ではない、自己判断での実践に孤立感と不安を覚えたのが、やめてしまった正直な理由の一つです。
【知っておきたい】「うつ消しごはん」を始める前の注意点
私の経験から、「うつ消しごはん」は素晴らしい可能性を秘めている一方で、試す前に知っておくべき注意点もあると感じています。
安全に食事法と向き合うための一般的な情報として、参考にしてください。
高タンパク食に関する一般的な留意点
タンパク質は体にとって不可欠ですが、腎臓の機能が低下している場合は、摂取量を制限する必要があります。
厚生労働省のサイトでは、以下のように解説されています。
通常の食事では(たんぱく質を)とりすぎになることはほとんどありませんが、腎臓の機能が低下している場合には、たんぱく質の摂取量を制限する必要があります。
(出典:厚生労働省 統合医療・情報発信サイト「たんぱく質」)
特に持病のある方は、自己判断でタンパク質の摂取量を大幅に増やすことは避けましょう。
サプリメントと医薬品の併用に関する一般的な留意点
サプリメント(健康食品)は、特定の成分を必要以上に摂ると健康を害する場合があることや、医薬品との相互作用について、専門機関から注意が促されています。
サプリメントと薬を一緒に飲むと、薬の効果が強くなったり弱くなったりすることがあるため、医師や薬剤師に相談することが大切です。
(出典:国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所「『健康食品』の安全性・有効性情報」)
特に、お薬を服用中の方は、自己判断でサプリメントを始めることは避け、必ず主治医や薬剤師に相談してください。
主治医への相談が不可欠である理由
うつ病の治療は、薬物療法、精神療法、そして休養が基本です。
食事療法はあくまで、これら主軸の治療を補助するものと考えるのが安全です。
薬との飲み合わせや、ご自身の体質に合う・合わないといった問題もあるため、新しい食事法を試す際は、必ず主治医に相談し、その指導のもとで行うようにしてください。
私の体験から考える「うつ消しごはん」と慎重に向き合うべき人
私の体験から、この食事法は素晴らしい可能性がある一方で、以下のような方は、実践をより慎重に検討した方が良いかもしれません。
- 胃腸が弱い方:プロテインやサプリでお腹の調子が悪くなる場合は、無理は禁物です
- 経済的な継続が難しい方:「お金の心配」が新たなストレスになるなら本末転倒です
- 日々の自己管理がストレスになりやすい方:毎日のサプリ管理や食事記録が「義務」に感じてしまうと、続けるのが苦しくなります
- (最も重要な前提として)主治医に相談せずに始めようとしている方:自己判断での実践は、予期せぬリスクを伴う可能性があります
そもそも「うつ消しごはん(藤川理論)」とは?
ここで改めて、「うつ消しごはん」の理論について、私が理解した要点を簡単にまとめます。
これは精神科医である藤川徳美先生が提唱する食事法です。
本の内容を詳しく知りたい方は、こちらの書籍で詳しく解説されています。
- 心の不調は「栄養不足」が原因と考える
脳内の神経伝達物質(セロトニンなど)を作るには、その材料となる「タンパク質」と「鉄」が不可欠であるという考え方が基本です。 - 糖質を減らし、タンパク質と鉄を増やす
日々の食事でパンや白米などの「糖質」を減らし、肉・卵・魚などの「タンパク質」をしっかり摂ることを推奨しています。 - サプリメントを積極的に活用する
タンパク質をエネルギーに変える効率を上げるため、プロテインやビタミンB群、ビタミンC、ビタミンEなどのサプリメントを積極的に摂ることが勧められています。
まとめ:「うつ消しごはん」と上手に付き合うための、私からの3つの提案
ここまで、私が「うつ消しごはん」を試して感じた良い変化と、やめてしまったリアルな理由についてお話ししてきました。
結論として、この食事法は「万人に効く魔法ではないが、食事を見直す良いきっかけになる選択肢の一つ」というのが、私の率直な感想です。
タンパク質やビタミンが心身の健康に重要であることは、間違いありません。
しかし、その一方で「継続の難しさ」「経済的な負担」「安全性への懸念」という壁があるのも事実です。
もしあなたが、この方法に興味があるのなら、私からお伝えしたいのは以下の3点です。
- 必ず、主治医に相談する
自己判断で始めるのではなく、まずは専門家である医師に相談し、安全性を確認してください。血液検査などで自分に何が足りていないのかを客観的に把握することが、遠回りのようで一番の近道です。 - いきなり完璧を目指さず「良いとこ取り」をしてみる
本に書かれている通りに実践しようとすると、心と財布に大きな負担がかかります。まずは「いつもの食事に少しだけタンパク質をプラスしてみる」など、無理のない範囲で試してみてはいかがでしょうか。 - 食事だけでなく、生活全体を見直す視点を持つ
回復のためには、食事だけでなく、睡眠や運動、休養といった基本的な生活習慣も同じくらい大切です。食事管理がストレスになるくらいなら、まずは生活全体を整えることから始めてみるのも一つの方法です。
この記事が、あなたの長いトンネルに、少しでも新しい光を灯すきっかけになれたなら、これほど嬉しいことはありません。
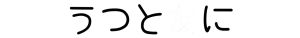
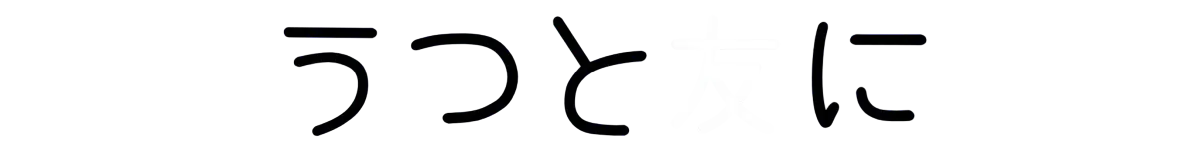
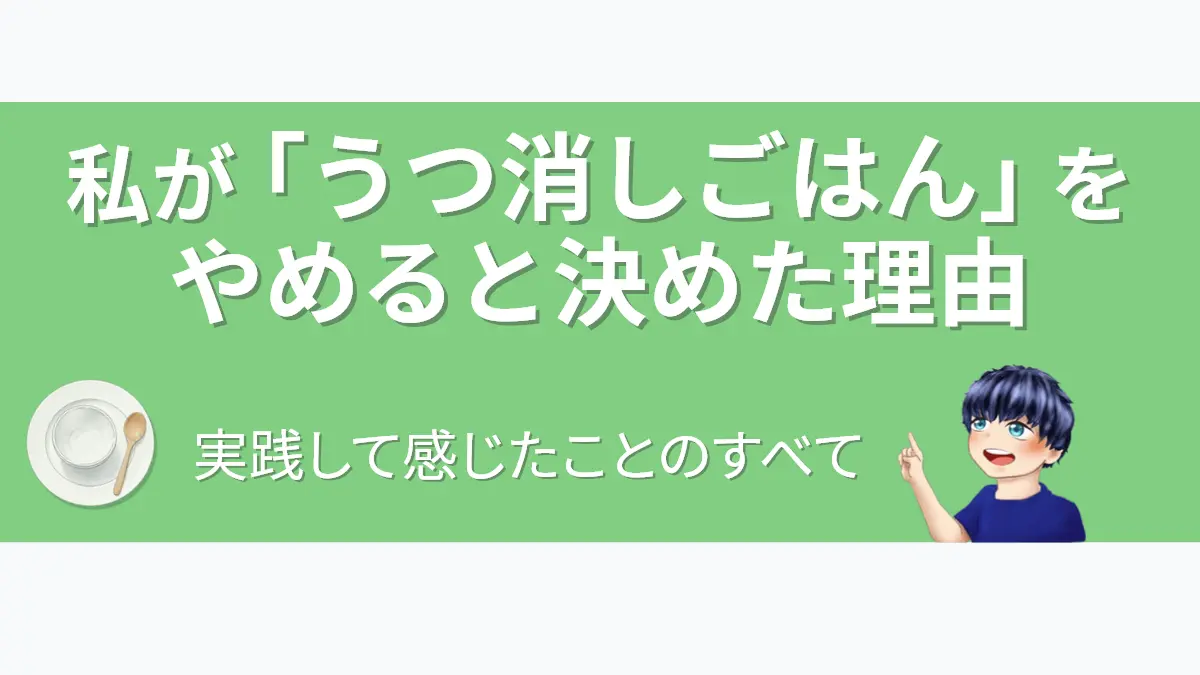
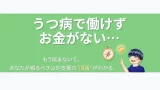
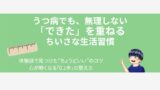
お気軽に感想をどうぞ