【体験談】うつ病で休職満了・自然退職…その後の不安が軽くなる制度活用と働き方
【導入】「もう、頑張らなくていい」――その言葉を、今、あなたに。
この記事は、うつ病で休職し、復職を目指して頑張ってきたけれど、それが叶わなかったあなたのためのものです。
「復職の許可が出なかった」
「休職期間が満了してしまった」
「会社に戻る気力が、どうしても湧かなかった」
今、あなたは深い無力感や、社会から取り残されたような絶望の中にいるかもしれません。
「自分はもう、社会復帰できない人間なんだ」と、自分を責めてしまっているのではないでしょうか。
でも、どうか聞いてください。
あなたのこれまでの努力は、何一つ無駄になっていません。
そして、何よりも伝えたいこと。
それは、「もう、これ以上、無理に頑張らなくていい」ということです。
復職だけが、社会復帰への道ではありません。
その道が閉ざされたのなら、それは「あなたに合わない道を進まなくていい」というサインです。
この記事では、かつてあなたと全く同じ経験をした私の体験をもとに、現実の受け止め方、生活を守る手続き、そして新しい働き方を見つけるまでの道のりを解説します。
大丈夫。道はちゃんとあります。
あなたのペースで、ゆっくりと読み進めてくださいね。
第1章【現実受容編】「復職できない」現実と向き合う、心の整理術
復職できないという現実は、あまりにも重く、すぐには受け入れがたいものだと思います。
まずは、その絡まった感情を少しずつ解きほぐし、冷静に「今」と向き合うことから始めましょう。

2度目の休職に入り、リワーク施設に通い始めたのですが、心が追いつかなかった。
朝起き上がれず、リワークを休みがちになり、「ああ、もう間に合わないな」と、日に日に現実が迫ってくるのがわかりました。
それは、ドラマのような劇的な絶望ではなく、じわじわと身体が冷たくなっていくような、静かな絶望でした。
そして迎えた、休職期間満了日。
会社からの連絡はなく、ただ就業規則に則って籍がなくなる。「自然退職」です。
誰を恨むわけでもない、ただ、当時の私は自分の不甲斐なさを感じ、社会から切り離されたような感覚で、心が重く沈んでいきました。。
【用語解説】自然退職とは?
会社の就業規則に定められた「休職期間」が満了しても復職できない場合に、自動的に雇用契約が終了すること。「解雇」や「会社都合退職」とは異なり、あくまで就業規則に基づく期間満了による退職として扱われます。
もしあなたが今、深い無力感の中にいるのなら、無理に前を向く必要はありません。
ただ、思考停止にだけは陥らないでほしいのです。
絶望から抜け出す、思考のスイッチ
そのために、私が実際にやってみて効果があった「思考の整理術」を紹介します。
頭の中だけで考えると、不安はどんどん大きくなっていきます。大切なのは、思考を「外に出して、目で見る」こと。
【体験談】私が実践した「人生のフローチャート」作成
当時、私はPowerPointを使って、自分の「ありうる未来」をすべて書き出すことから始めました。
- まず、今の自分の状況(退職、うつ病療養中など)を書き出す。
- そこから矢印を伸ばし、現実的かどうかは一旦無視して、すべての可能性を書き出す。(例:フリーランスになる、専業主夫になる、実家に帰る、アルバイトを始める、など)
- さらに矢印を伸ばし、それぞれのメリット・デメリットなどを書き加えていく。
最初は荒唐無稽に見える地図でも、それを妻や医療ソーシャルワーカー(MSW)に見せながら対話することで、「これは現実的じゃないね」「こっちの可能性を探ってみようか」と、客観的な視点で選択肢を絞り込んでいくことができました。
この「可視化」と「対話」が、暗闇の中で進むべき道を照らす、最初の光になったのです。
「これから、どうなれる可能性があるだろう?」
そう自分に問いかけ、心を整理する時間を作ってみてください。
第2章【生活防衛編】退職後の不安を解消する、お金と手続き
心の整理と同時に進めたいのが、最も現実的な不安である「お金」の問題です。
「明日からの生活はどうなるんだろう…」という不安は、冷静な判断を奪います。
大丈夫。あなたが路頭に迷うことがないよう、国にはしっかりとしたセーフティネットが用意されています。
まずは手続きを済ませ、具体的な見通しを立てることで、「焦らなくてもいいんだ」という安心感を手に入れましょう。
ステップ1:退職手続きのチェックリスト
会社との最後のやり取りを、確実に行いましょう。
特に「離職票」は、失業保険の給付に不可欠な最重要書類です。
退職時に必ず確認・受領する書類
- 離職票(-1、-2):失業保険の申請に必須。後日郵送される場合が多い。
- 雇用保険被保険者証:失業保険の申請に必要。
- 年金手帳:国民年金への切り替え手続きに必要。
- 源泉徴収票:確定申告や、次の職場の年末調整に必要。
- 健康保険資格喪失証明書:国民健康保険への切り替え手続きに必要。
【最重要ポイント】離職票の「離職理由」を確認!
離職票-2に記載される「離職理由」は非常に重要です。
うつ病などが原因で自己都合退職した場合、「正当な理由のある自己都合退職」として扱われ、失業保険の給付制限(通常2ヶ月)がなくなる可能性があります。会社の担当者がこの点を理解していない場合もあるため、もし離職理由に相違があれば、ハローワークで事情を説明しましょう。最終的な判断はハローワークが行いますが、主治医の意見書などが有力な判断材料になります。必ずしも認められるとは限りませんが、少しでも不安な点があれば、まずは窓口で相談することが重要です。
ステップ2:あなたの「生活防衛資金」を計算しよう
あなたが今後、どれくらいの期間、経済的な心配をせずに療養や準備に専念できるか、一度計算してみましょう。
主に活用できるのは、以下の3つの制度です。
| 制度名 | 内容の目安 | ポイント |
|---|---|---|
| (1) 退職金 | 会社の就業規則による | 自己都合退職の場合、満額は出ないことが多いですが、重要な資金源です。まずは規定を確認しましょう。 |
| (2) 傷病手当金 | 給与のおよそ2/3が、原則最長1年6ヶ月間支給 | 退職後も継続して受給できる場合があります(任意継続給付)。療養中の生活を支える最大の柱になります。 ※詳細は全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式サイトをご確認ください。 |
| (3) 失業保険(雇用保険) | 働ける状態になってから、90日~150日間支給 | うつ病が理由の退職は「正当な理由のある自己都合退職」となり、給付制限なしで受給できる場合があります。 ※詳細はハローワークの公式サイトをご確認ください。 |
これらを合計することで、「少なくともこれだけの期間は大丈夫」という具体的な見通しが立ち、精神的な余裕が生まれます。
ステップ3:傷病手当金と失業保険を切れ目なく活用する
うつ病で退職した場合、生活を守る上で非常に重要になるのが、この2つの制度を続けて受け取る方法です。
以下の流れを、まずは頭に入れておきましょう。
- 退職後、まずは傷病手当金を受給して、療養に専念する。
- 並行して、ハローワークで「失業保険の受給期間延長」の手続きを行う。(退職日の翌日から30日以内に申請が必要)
- 体調が回復した、または傷病手当金の受給期間が満了するタイミングで、主治医に相談する。
- 就労可能と判断されたら、ハローワークで延長解除の手続きを行い、失業保険の受給を開始する。
※注意:これらの制度の適用条件や受給額は、ご自身が加入している健康保険組合や雇用保険の加入期間など、個々の状況によって異なります。この記事はあくまで一般的な流れを示すものですので、必ずお近くのハローワークや年金事務所、健康保険組合の窓口で直接ご相談ください。

おかげで、退職後約1年間は傷病手当金で生活の心配をせず、療養と今後の準備に集中できました。
「受給期間の延長申請」は少し面倒に感じるかもしれませんが、これをやっておくかどうかで、その後の安心感が全く違います。できる範囲で、早めに手続きをしておくと安心ですよ。
第3章【未来設計編】退職後の選択肢は、一つじゃない
生活の不安が和らいだら、いよいよ「これから」について考えていきましょう。
ここで最も大切なことを、先にお伝えします。
「すぐに転職すること」だけが選択肢ではありません。
これは、私自身も一度焦ってしまい、遠回りすることで学んだ教訓です。
特に、復職が叶わなかったあなたは、心身のエネルギーが大きく消耗しているはずです。
焦って次の職場を決めても、また同じことの繰り返しになりかねません。
今のあなたの心境に合わせて、気になる項目から読んでみてください。
今のあなたの心は、どの状態に近いですか?
- A. まだ何も考えられない、とにかく休みたい → まずは「選択肢1」を読んで、焦る必要がないことを確認してください。
- B. 少しだけ、社会との繋がりを取り戻したい → 「選択肢1」と「選択- 2」が参考になるかもしれません。
- C. 具体的な仕事探しについて考え始めたい → 「選択肢2」と「選択肢3」を読んでみてください。
選択肢1:社会との”やさしい”接点を取り戻す(就労支援の活用)
いきなり週5日のフルタイム勤務に戻るのではなく、まずは短い時間から社会参加の練習ができる公的なサービスがあります。
それが「障害福祉サービス(就労支援)」です。
サービスは多岐にわたりますが、この記事では、私が実際に利用して「次への大きな一歩」になった「自立訓練(生活訓練)」の体験談を紹介します。
(※各サービスの詳細については、後日別の記事で詳しく解説しますね)
【体験談】自立訓練作業所に通って見えた光
私が通った作業所は、週2日から、1日4時間程度の利用が可能でした。主な活動は、軽作業やPC訓練、コミュニケーションを学ぶグループワークなどです。
正直、最初は「こんな簡単なことで意味があるのかな」と思っていました。でも、違ったんです。
- 「決まった時間に、決まった場所へ行く」という行為が、生活リズムの最高の土台になった。
- 同じような痛みや悩みを抱える仲間と出会い、「自分だけじゃなかったんだ」と心から思えた。
- 職員の方に、仕事だけでなく生活全般の相談に乗ってもらえた。
何より大きかったのは、「ここはゴールじゃない。あくまで社会復帰へのリハビリ場所なんだ」という安心感の中で、自分のペースで自信を少しずつ取り戻せたことです。私にとって、この期間は本当に価値のあるものでした。
少しでも気になったら、まずはお住まいの市区町村の障害福祉課に相談してみてください。障害者手帳がなくても、医師の診断書で利用できる場合があります。
選択肢2:新しい働き方を探す旅(ハローワーク・転職エージェント)
ある程度、心身が回復してきたら、具体的な仕事探しも視野に入ってきます。

【体験談】転職に至らなかった私のハローワーク体験記
私も、失業保険の給付を受けながらハローワークに通いました。
障害者求人の窓口で相談に乗ってもらい、いくつか求人も紹介してもらいましたが、結局、応募には至らなかったんです。
求人票を見ても、「またあんな風に働けるだろうか」という不安が先に立ち、心が動かない。
面接に進むことを想像するだけで、自信のなさがこみ上げてくる。
そんな状態でした。
でも、今思えば、この「うまくいかなかった経験」も無駄ではありませんでした。
「ああ、自分はまだ、フルタイムで働く準備ができていないんだな」という現実を、身をもって知ることができたからです。
転職活動は、必ずしも「内定」がゴールではありません。自分の現在地を知るための、大切なプロセスでもあるのです。
ハローワーク以外にも、うつ病など精神障害のある方の就職・転職に特化した民間の「転職エージェント」もあります。
専門のキャリアアドバイザーが、企業との間に入って、病気への配慮などを交渉してくれるのが大きな強みです。
選択肢3:働き方のスタイルを選ぶ(オープン/クローズ)
いざ働くとなった時、多くの人が悩むのがこの問題です。
- オープン就労:病気や障害のことを会社に開示して働くスタイル。必要な配慮(通院、時短勤務、業務内容の調整など)を受けやすいのがメリット。一方、給与やキャリアパスに制約が出る可能性もあります。
- クローズ就労:病気や障害のことを開示せずに働くスタイル。オープン就労に比べて、仕事の選択肢や待遇面の幅が広がる可能性があります。一方、必要な配慮を得にくく、再発のリスク管理はすべて自己責任となります。
どちらが正解ということはありません。
あなたの体調、求める働き方、そしてキャリアプランを総合的に考えて、主治医や支援機関のスタッフとも相談しながら、自分に合ったスタイルを選んでいきましょう。
【まとめ】あなたの物語は、ここから始まる
ここまで、復職が叶わなかった後の「次の一歩」について、私の体験を交えながら解説してきました。
復職できなかったという経験は、あなたの価値を何一つ傷つけるものではありません。
むしろ、それは「あなたに合わない働き方から、卒業できた」という、新しい始まりの合図です。
最後に、この記事でお伝えした3つのステップを振り返ってみましょう。
- 現実を受け入れる:まずは感情と事実を整理し、客観的に自分を見つめ直す。
- 生活を守る:公的な制度をフル活用し、お金の不安から解放される。
- 未来を設計する:焦らず、自分に合った「次の一歩」の選択肢を知る。
どうか焦らないでください。
まずはしっかり休み、自分を労わる時間を何よりも大切にしてください。
あなたの物語は、決して終わりではありません。
ここから、あなただけの新しい物語が始まるのです。
その一歩を、心から応援しています。
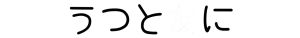
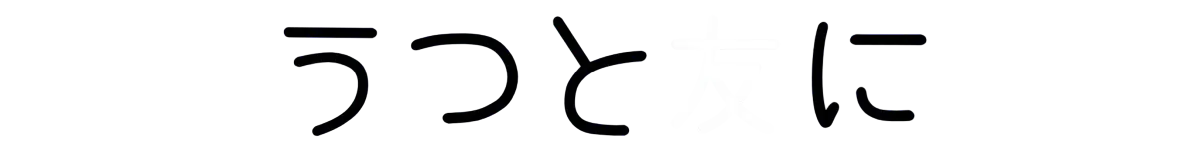
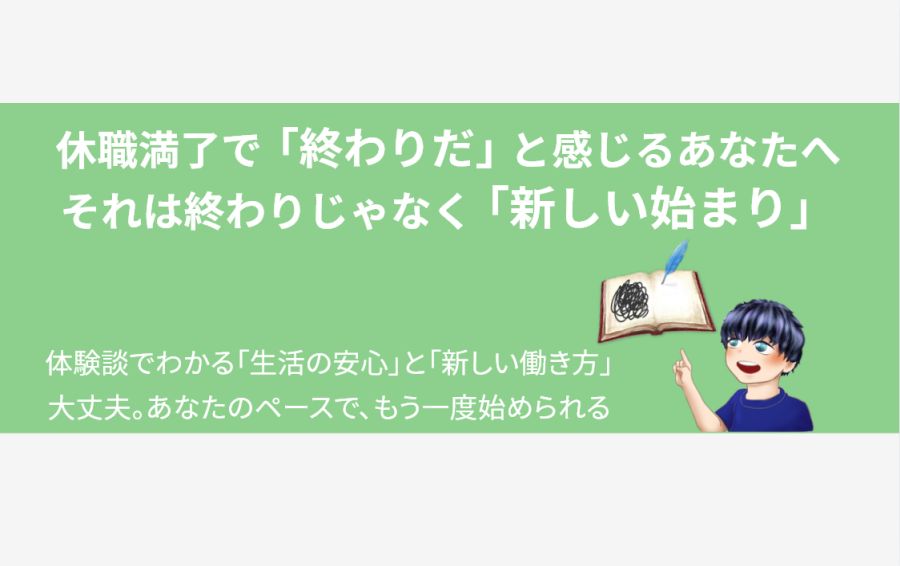
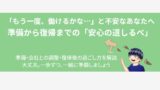
お気軽に感想をどうぞ