
保護者の方だけでなく、ご自身の症状に「もしかして…」と不安を感じている方もいるかもしれません。


この記事でお伝えしたいこと
この記事では、かつて昼夜逆転に苦しみ、社会人になってから「概日リズム睡眠障害」と診断された私の体験も交えながら、
- 起立性調節障害ってどんな病気?
- うつ病との違いや関係は?
- 周りに理解されないつらさとどう向き合うか
- 当事者と家族が、今日からできること
について、一緒に考えていきたいと思います。
もう一人で悩ないでください。この記事が、あなたの心を守るヒントになれば嬉しいです。
起立性調節障害(OD)とは?「なまけ病」ではない、体の病気です
「朝起きられない」
「午前中はぐったりして、午後になると少し元気が出てくる」
「立ち上がるとめまいや動悸がする」
もし、あなたやお子さんにこんな症状があるなら、それは「起立性調節障害(Orthostatic Dysregulation: OD)」かもしれません。
簡単に言うと、立ち上がった時に自律神経がうまく働かず、脳や体への血流が一時的に低下してしまう病気です。
その結果、朝起き上がれなかったり、めまい、頭痛、吐き気、倦怠感といった様々な症状が現れます。
本人の意思とは関係なく、体がうまく機能しない状態であり、決して「なまけ」や「根性がない」からではありません。
私の体験談:「怠け」のレッテルと、診断されない苦しみ
今思えば、これも起立性調節障害の症状とよく似ていたなと感じます。
幼稚園のお昼寝時間は一度も眠れず、小学校の夏休みは昼夜逆転。高校生になる頃にはそれが当たり前になり、不登校気味になりました。
当時つらかったのは、周囲の目です。
直接「怠け者」と言われたわけではありませんが、「なんで学校来てないのに、テストで赤点取らないの?」と不思議がられている空気を感じていました。家で一人、必死に勉強して遅れを取り戻していたのですが、その背景までは伝わりません。
私が学生だった約30年前は、起立性調節障害という病名自体は存在していましたが、一般にはほとんど知られていませんでした。そのため、病院で相談するという発想もなく、診断されることはありませんでした。
社会人になりうつ病を発症してからようやく専門医にかかり、私は「概日リズム睡眠障害」(※)という診断を受けました。
※体内時計のリズムがずれて、社会的に望ましい時間帯に睡眠・覚醒することが難しくなる睡眠障害の一種です。
この体験から、私は「周囲に理解されないつらさ」と「適切な診断の重要性」を痛感しました。この記事では、その両方の視点から解説していきます。
【重要】起立性調節障害とうつ病の関係性
起立性調節障害の症状は、うつ病の症状と似ている部分があります。
- 朝起きられない
- 体がだるい、疲れやすい
- 集中力・思考力が低下する
- 食欲がない
そのため、両者は間違われやすく、時には併発することもあります。
また、もし立ちくらみなどの身体症状はなく、ただ「鉛のような体の重さ」や「強い絶望感」で起き上がれない場合は、うつ病特有の「日内変動」が原因かもしれません。
当事者が一番つらいのは「周りに理解されないこと」
病気の症状そのものもつらいですが、起立性調節障害の当事者が本当に苦しむのは、周囲からの無理解からくる「孤独感」や「罪悪感」なのかもしれません。

私たちにできること|当事者と家族のヒント
では、このつらい症状とどう向き合っていけばいいのでしょうか。
専門学会の情報を参考に、「当事者本人にできること」と「家族ができること」に分けてまとめました。
当事者本人にできること|自分を責めずに試せる工夫
まずは、自分自身をこれ以上責めないことが大切です。その上で、少しでも症状を和らげるために、生活の中で試せるとされている工夫をいくつか紹介します。
家族(親)ができること|一番の薬は「理解」です
お子さんの症状に悩むご家族の方へ。
私が自分の経験を通して、そして多くの当事者の声を聞いてきて、一番大切だと感じることをお伝えします。

「学校に行きたくない」のではなく、「行きたくても、行けない」のです。
その苦しみを一番近くで理解し、「あなたのせいじゃないよ」と伝え続けてあげることが、何よりの薬になります。
その上で、具体的なサポートとして以下のことを心がけてみてください。
- 無理に起こさない:焦る気持ちはわかりますが、無理やり起こすことは症状を悪化させるだけでなく、本人のプレッシャーにもなります。
- 学校と連携する:診断書などを基に、病気について学校側の理解を求めましょう。別室登校や、午後からの登校など、無理のない形を相談することが大切です。
- 本人の気持ちに寄り添う言葉を選ぶ:「頑張れ」「早く寝ないからだ」といった言葉は、本人を追いつめます。励ましのつもりが、深い罪悪感を植え付けてしまう可能性があることを理解し、まずは本人のつらさを受け止める言葉をかけてあげてください。
まずは専門医へ相談を|何科に行けばいい?
「もしかして…」と思ったら、自己判断で抱え込まず、まずは専門の医療機関を受診することが回復への一番の近道です。
- 子ども(中学生以下)の場合:まずはかかりつけの「小児科」に相談しましょう。起立性調節障害の専門外来がある病院を紹介してもらえることもあります。
- 高校生以上・大人の場合:「内科」「循環器内科」「神経内科」、あるいは気分の落ち込みなど精神的な症状もあれば「心療内科」が選択肢になります。
病院では、血圧測定などの検査を通じて、症状の裏に他の病気が隠れていないかもしっかりと調べてくれます。
私の経験からも、専門家に相談することで「自分のせいじゃなかったんだ」と分かり、心が軽くなるという側面も非常に大きいです。
まとめ:「一人じゃない」と思えることが、回復の光になる
この記事では、起立性調節障害の基本的な知識から、うつ病との関係、そして当事者と家族ができることについて、私の体験を交えながらお話ししました。
朝、目が覚めても体が動かない絶望感
行かなければいけない場所に行けない罪悪感
そして、誰にもこのつらさをわかってもらえない孤独感
もしあなたが今、そんな暗闇の中にいるのなら、どうか思い出してください。
あなた一人ではありません。
同じように苦しみ、そして少しずつ光を見つけて歩いている仲間が、ここにいます。
この記事が、その暗闇を照らす小さな光となることを、心から願っています。
参考文献
- 日本小児心身医学会 「起立性調節障害」 2025年11月21日閲覧
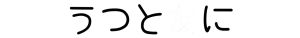
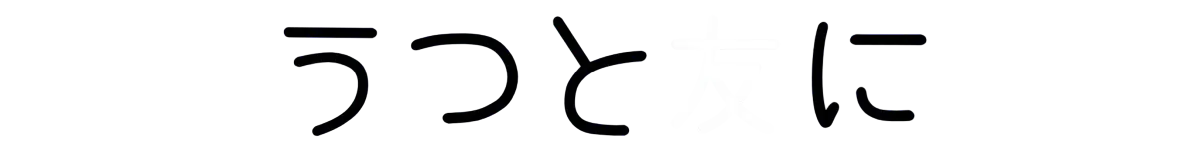
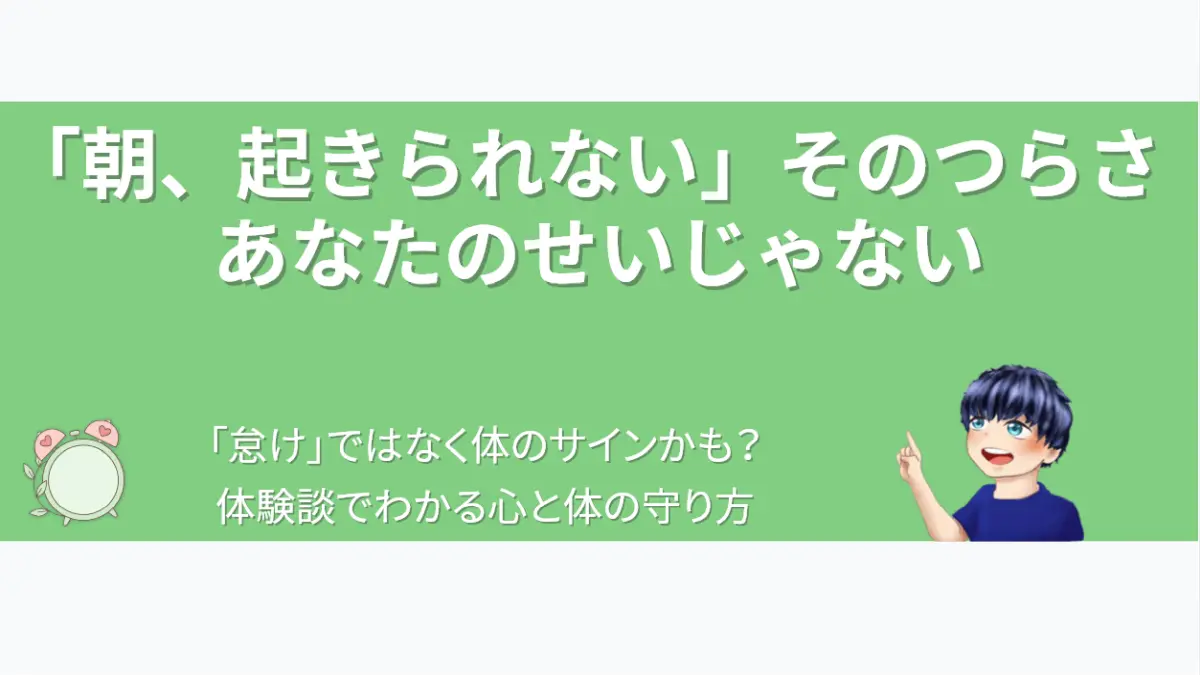
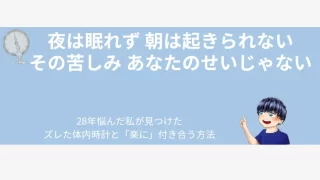
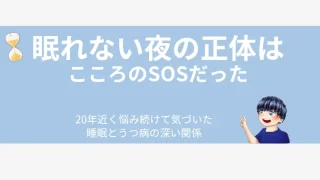

お気軽に感想をどうぞ