この記事を読めば、うつ病で退職したあなたが「お金の不安を軽くして、安心して療養するための失業保険のもらい方」がわかります。
特に「うつ病で退職したばかりで不安を感じている方」「すぐに就職するのが難しい状況の方」にとって、きっと役立つ内容です。
「すぐに働ける状態じゃないのに、生活費はどうしよう…」
「ハローワークに行くのが辛い…」
退職後の生活への不安と、次に進めなければいけないというプレッシャー。
私自身、そんな辛い経験をしたからこそ、あなたの気持ちが痛いほどわかります。
でも、大丈夫です。
この記事では、「就職困難者」という制度を中心に、あなたのペースで無理なく失業保険を受け取る方法を、私の体験談を交えながら丁寧に解説します。
うつ病で退職後にもらえる失業保険の基本【3つのポイント】
失業保険とは、会社を辞めて失業中の人が、生活の心配をせずに新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう支援するための制度です。
まずは、基本となる3つのポイントを押さえておきましょう。
ポイント1:もらえる条件・金額・期間
失業保険をもらうには、原則として「働きたいという意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」であることが必要です。
- もらえる金額:離職前の賃金によって決まります。
- もらえる期間:年齢や雇用保険の加入期間、離職理由によって変わります。
ポイント2:退職理由の分類
離職理由は、大きく分けて「自己都合」「会社都合」があります。
うつ病など体調不良が原因で、休職期間満了により退職となるケースもあります。
ポイント3:うつ病が理由なら「正当な理由のある自己都合退職」になる可能性
「自己都合」で退職すると、通常は2ヶ月間の給付制限(失業保険がもらえない期間)があります。
しかし、うつ病などの体調不良が原因で退職した場合は、「正当な理由のある自己都合退職」と判断され、この給付制限がなくなる可能性が高いです。
申請時に医師の診断書などを添えて事情を説明することが大切ですが、最終的な判断はハローワークが行います。
【体験談あり】うつ病なら知っておきたい「就職困難者」とは?メリットと認定条件
ここからが、この記事で最もお伝えしたい大切なポイントです。
うつ病などの病気が理由で、すぐに働くことが難しい人は、「就職困難者」として認定される可能性があります。
「就職困難者」認定のポイント
- 医師による「(フルタイムでの就労は難しいが)就労は可能である」といった内容の診断書や意見書が重要になります。
- 精神障害者保健福祉手帳の有無は、必須ではないことが多いです。
- 最終的な判断は、提出された書類などを元にハローワークが行います。
つまり「就職困難者」に認定されると、一般の離職者よりも手厚いサポートを受けながら自分のペースで再就職を目指せるようになります。
具体的には、3つの大きなメリットがあります。
メリット1:給付日数が最大360日に増える
最大のメリットは、失業保険をもらえる期間が大幅に増えることです。年齢や被保険者期間によって異なりますが、一般の離職者に比べて日数が延長され、経済的な安心を得やすくなります。
私もこの制度のおかげで、給付日数が300日になりました。おかげで「すぐ仕事を見つけなきゃ」という焦りから解放され、じっくりと治療に専念しながら自分のペースで次の一歩を考えることができました。
メリット2:求職活動を自分のペースで進められる
就職困難者の場合、ハローワークの担当者があなたの病状や体調を理解した上で、無理のない活動計画を一緒に考えてくれます。

私の場合、求職活動の回数が月に1回に緩和されました。そして、その活動内容も、ハローワークの窓口で担当者の方に「最近の体調はどうですか?」といった相談をすることが、正式な求職活動実績として認められました。「すぐに求人に応募しなくてもいい」と知るだけで、心の負担が驚くほど軽くなりました。
メリット3:受給資格の条件が緩和される
通常、失業保険をもらうには「離職日以前2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上」必要です。
しかし、就職困難者の場合は、この条件が「離職日以前1年間に、被保険者期間が6ヶ月以上」に緩和されます。
【図解】失業保険の申請から受給までの全ステップ
ここでは、具体的な手続きの流れを解説します。
特に、傷病手当金を受給中の方は、Step0が非常に重要です。
- Step0受給期間の延長申請傷病手当金を受給中はまずコレ!療養に専念
- Step1申請の準備体調回復後、必要書類と診断書を用意
- Step2ハローワークで本申請管轄の窓口で「就職困難者」として手続き
- Step3認定・受給開始月1回の認定を受け、自分のペースで活動へ
Step0:【傷病手当金を受給中のあなたへ】まずは「受給期間の延長」を!
「まだ働ける状態じゃない…」という場合は、退職後すぐに失業保険を申請するのではなく、まず「受給期間の延長」手続きを行いましょう。
これは、失業保険を受け取れる権利の有効期間を、本来の「離職日の翌日から1年間」に加えて、さらに最大3年間延長できる制度です。つまり、離職日の翌日から最長で4年先まで、申請を先延ばしにできます。

私も退職時は傷病手当金をもらっていたので、まずこの延長手続きをしました。おかげで、焦ることなく治療を続けられ、約2年後、自分にとってベストなタイミングで申請に移行できました。この手続きを知っているかどうかで、その後の療養生活が大きく変わります。
Step1:準備編 – 最小限の外出で済ませるために
体調が回復し、いざ申請へ。
ハローワークへ行く前に、必要なものをしっかり準備しましょう。
申請に必要なものリスト
- 雇用保険被保険者離職票(1と2)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- 身元確認書類(運転免許証など)
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm)
※写真の代わりにマイナンバーカードを持参することも可能です。その場合、写真は不要になりますが、マイナンバーカードは認定日ごとに毎回提示が必要です。 - 印鑑
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 医師の診断書または意見書(就職困難者として申請する場合)
Step2:いざハローワークへ – 無駄足を踏まないための最重要ポイント
準備が整ったら、あなたの住所を管轄するハローワークへ行きます。
ここで、心身の消耗を避けるための最重要ポイントがあります。
Step3:失業認定と「無理しない」求職活動
申請が受理されると、原則として4週間に1度、失業の認定日にハローワークへ行き、「失業認定申告書」を提出します。
このとき、期間中に行った求職活動を報告します。
私は主に「ハローワークでの職業相談」で実績を報告していました。また、自宅から求人情報を検索できる「ハローワークインターネットサービス」にプロフィールをしっかり登録しておくことで、「働く意思があります」という姿勢を示すことにも繋がります。
うつ病当事者が抱える「3つの壁」と具体的な乗り越え方
制度はわかっても、いざ行動するとなると、心と体がついていかないこともありますよね。
ここでは、当事者ならではの「3つの壁」と、その乗り越え方をお伝えします。
壁1:体調が悪くて、ハローワークに行けない…

当時、私はこの方法を知らずに無理して通いましたが、あなたには同じ思いをしてほしくありません。原則は本人の来所が必要ですが、医師の証明書などを提出することで、代理人や郵送での手続きが認められる場合があります。必要な書類や条件は状況によって異なるため、必ず事前に管轄のハローワークへ電話で相談してください。
壁2:「求職活動しなきゃ」というプレッシャーが辛い…
「就職困難者」に認定されるということは、ハローワーク側も「すぐに就職するのが難しい状態」だと理解してくれています。
「すぐに求人に応募すること」だけが求職活動ではありません。
まずは担当者に「治療と並行しながら自分のペースで仕事を探したいです」と、あなたの意思を誠実に伝え、月1回の職業相談から始めることを目標にしましょう。
壁3:職員に病状をどう説明すればいい?
このように、「できること(ハローワークの基準を満たしていること)」と「自分の希望」を具体的に伝えると、担当者もサポートしやすくなります。
うつ病と失業保険でよくある質問(FAQ)
傷病手当金との切り替えはどうすればいいの?
記事のStep0でお伝えした通り、傷病手当金を受給中は、まず「受給期間の延長」手続きを行うのが鉄則です。体調が回復し、主治医から「就労可能」の診断が出たタイミングで、傷病手当金の受給を終了し、失業保険の本申請に切り替えます。
受給中にまた体調が悪化したらどうなる?
再び働けない状態になった場合は、失業保険の受給を一時ストップし、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合に申請して「傷病手当金」に切り替えることができます。焦らず、まずは治療に専念しましょう。
受給中にアルバイトはできる?B型作業所の工賃は?
週20時間未満など、一定の条件下でアルバイトをすることは可能です。ただし、働いた日や収入は、失業認定申告書で必ず正直に申告する必要があります。申告を怠ると不正受給となるため注意してください。
なお、就労継続支援B型事業所の工賃は、雇用契約に基づく「賃金」ではないため、原則として収入申告の必要はないことが多いですが、自治体やハローワークの判断によって扱いが異なる場合があるため、必ず事前に管轄のハローワークに確認してください。
失業保険は確定申告が必要?
いいえ、失業保険は非課税所得ですので、確定申告は不要です。所得税も住民税もかかりません。
再就職活動はいつから始めるべき?
焦る必要はまったくありません。まずは生活リズムを整え、心と体を休めることが最優先です。受給期間中にハローワークの担当者と相談しながら自分のペースで「どんな働き方がしたいか」を考えたり、情報収集を始めたりするのがおすすめです。
【まとめ】焦らず、あなたのペースで。失業保険は、次の一歩を踏み出すための大切な「時間」です
失業保険は、単なるお金の支援ではありません。
経済的な安心を得て、治療に専念し、あなた自身のペースで社会復帰を目指すための、大切な「時間」を確保してくれる制度です。
この記事が、あなたの不安を少しでも軽くし、次の一歩を踏み出すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
あなたが今日からできる2つのこと
- 主治医に相談する
「失業保険の受給を考えているのですが、就労可能という内容で診断書を書いてもらうことはできますか?」と、まずは相談してみましょう。 - ハローワークに電話してみる
「失業保険のことで聞きたいのですが」と、一本の電話で管轄や必要なものを確認するだけでも、大きな一歩です。
私も、この制度に救われた一人です。
失業保険というセーフティネットをしっかり活用し、焦らず、あなたのペースで再出発の準備をしてください。この「時間」が、きっと未来のあなたを支える力になります。
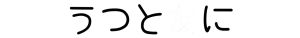
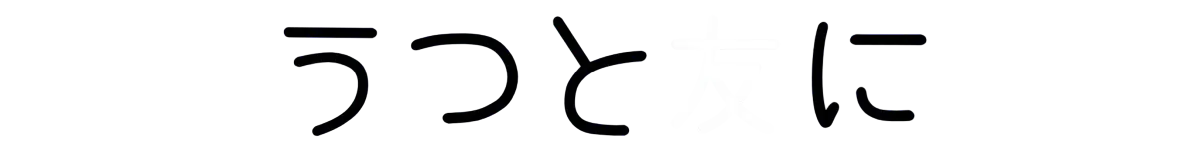
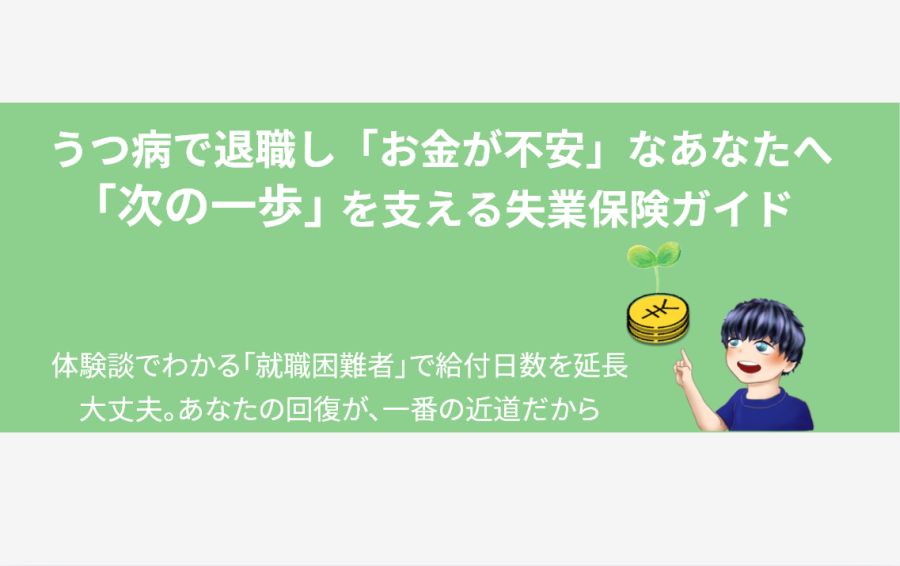
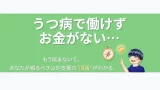
お気軽に感想をどうぞ