うつ病の治療でお休みしていると、「自分だけ時間が止まっているような気がする」——そんな瞬間に、ふと襲われることはありませんか。
「もう一度、働きたいな…」
そう思う気持ちとは裏腹に、心と体は思うように動いてくれない。
スマホで求人を眺めては、ため息と一緒に閉じてしまう。
そんな毎日が、ただただ過ぎていく…。
私も、ずっとそうでした。
そんな時、病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)さんから「こういう選択肢もありますよ」と教えてもらったのが、「就労支援」でした。
でも、正直、最初は怖かったです。
「どんな人がいるんだろう?」
「厳しい場所だったらどうしよう…」
「そもそも、お金はかかるのかな?」
わからないことだらけで、一歩を踏み出すのがとても不安でした。
これは難しい制度の解説書ではありません。うつ病当事者として実際に「自立訓練」というサービスに1年間通い、そして今は「休所」している私が、中で見て、感じた「光」も「影」も、すべて正直にお伝えする、少し未来のあなたからの手紙です。
焦らないで大丈夫。
まずは一緒に、扉の向こう側をそっと覗いてみませんか?
【基本】就労支援とは?うつ病の社会復帰を支える制度
「就労支援」と聞くと、少し堅苦しいイメージがあるかもしれませんね。
でも、もっとシンプルに考えて大丈夫。
一言でいうと、社会復帰に向けた、心と体のリハビリ施設のような場所です。
あなたの今の状態に合わせて、社会に戻るためのステップを、ゆっくりと一緒に歩んでくれます。
4つのステップでわかる就労支援の全体像
主に、こんな4つのステップ(サービス)が用意されていますよ。
- STEP1準備段階:自立訓練(生活訓練)「まずは、生活リズムを整えたい」「安定して外出できるようになりたい」という方のための場所です。コミュニケーション講座や軽作業などを通して、社会生活の土台を作ります。私が利用したのは、このサービスです。
- STEP2実践段階①:就労移行支援一般企業への就職を具体的に目指す方のための、より実践的なスキルを学ぶ場所です。PCスキルの習得、応募書類の作成、模擬面接など、就職活動に必要なスキルを身につけます。
- STEP3実践段階②:就労継続支援B型「フルタイムで働くのはまだ不安」「自分のペースを大切にしたい」という方のための場所。雇用契約は結ばず、簡単な作業などを通して、働くことに慣れていきます。作業量に応じて「工賃」が支払われます。
- STEP4実践段階③:就労継続支援A型事業所と雇用契約を結び、支援を受けながらしっかりと働く場所です。最低賃金以上の「給料」が保証されており、社会保険に加入できる場合もあります。
【お金の不安を解消】就労支援の費用・工賃・手当のすべて【一覧表つき】
サービスを利用するにあたって、きっと一番気になるのが「お金」のことですよね。
私もそうでした。
でも、安心してください。
金銭的な負担をできるだけ軽くするための仕組みが、ちゃんと整えられています。
利用にかかる費用は?(自己負担額)
サービスの利用料金は、あなたやご家族の前年の所得(世帯所得)によって決まりますが、上限額が設定されています。
| 世帯の所得区分 | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 上記以外 | 37,200円 |

工賃や給料はもらえるの?
サービスの種類によって、収入を得られるかどうかが変わります。
| サービスの種類 | 収入の種類 | 備考 |
|---|---|---|
| 自立訓練 / 就労移行支援 | 原則なし | あくまで「訓練」が目的のため、基本的に収入は発生しません。 ※事業所によっては、B型の作業を手伝う等で少額の工賃が発生する場合もあります。 |
| 就労継続支援B型 | 工賃 | 作業内容や時間に応じた工賃が支払われます。(※1) |
| 就労継続支援A型 | 給料 | 雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給料が支払われます。 |
※1 出典:令和5年度工賃(賃金)の実績について|厚生労働省(全国平均月額:23,053円)
【最重要】傷病手当金や失業保険をもらいながら通える?
休職・離職中の生活を支える各種手当。
これらを受け取りながら、サービスを利用できるのかは、とても重要な問題ですよね。
ひとつずつ解説していきます。
傷病手当金との併用
傷病手当金は「働けない状態」の人が対象のため、原則として「働くための訓練」である就労支援との併用は難しいとされています。
ただし、主治医が「『就労の準備段階として適切なリハビリ』と判断した」場合に限り、あなたが加入している健康保険組合が許可すれば、通所が可能なケースもありますが、非常に例外的です。
失業保険(雇用保険)との併用
失業保険は「働く意思と能力がある人」が対象です。
就労支援への通所が「就職に向けた積極的な活動(求職活動)」の一環と認められれば、失業認定日にその実績を報告することで、給付を受けながら通うことができます。
私も実際に、ハローワークの担当者さんに相談し、許可を得てから通い始めました。
障害年金・生活保護との併用
障害年金や生活保護は、就労支援サービスとの併用が可能です。
年金や生活保護費を受給しながら、無理のない範囲でサービスを利用し、社会復帰を目指すことができます。
むしろ、ケースワーカーさんから利用を勧められることもありますよ。
【まとめ】各種手当との併用可否一覧
| 傷病手当金 | 失業保険 | 障害年金 | 生活保護 | |
|---|---|---|---|---|
| 併用可否 | 原則難しい (要確認) |
可能 (要確認) |
可能 | 可能 |
【本編】私が体験した「自立訓練」の光と影(通ってわかったメリット・デメリット)
お金の不安が少し和らいだところで、いよいよ、私のリアルな体験談をお話ししますね。
光(メリット・通ってよかったこと)
私が通っていた事業所は、うつ病など心の不調を抱える大人だけでなく、車椅子を利用している方や、発達障害のお子さんとその親御さんなど、本当に様々な方が利用する、とても開かれた場所でした。
だからこそ、変に壁を感じることなく、自然体でいられたのかもしれません。
そんな環境で私が感じた「よかったこと」は、主に以下の3つです。
- 「行く場所」があるという安心感:家に引きこもりがちだった私にとって、決まった時間に外に出て、誰かと挨拶を交わすという習慣は、心と体を少しずつ元気にしてくれました。
- 職員さんとの心地よい距離感:引きこもりがちな生活で人との交流がほとんどなかった私にとって、利用者同士で無理に交流する必要がなく、それでいて困ったときには親身に話を聞いてくれる職員さんがいる、という距離感が何より心地よかったです。
- 自分のペースで進められたPC作業:講座への参加は必須ではなく、私は自分のペースでPC作業をさせてもらえました。毎日少しずつでも作業を進めることが、自信を取り戻すための良いリハビリになりました。
影(デメリット・つらかったこと)
もちろん、良いことばかりではありませんでした。
- 過去の自分と比べてしまう焦り:周りの人と比べることはありませんでしたが、だんだん通えなくなっていく自分を、以前の元気だった自分と比べては「情けない」と感じて落ち込むことが多かったです。
- 体調の波に左右されるもどかしさ:「今日は行けそう」と思って準備をしても、急に気分が落ち込んで動けなくなる。そんな自分をもどかしく、情けなく感じていました。
- 苦手な作業への戸惑い:私は手先を使う細かい作業が苦手なのですが、プログラムでそうした作業があった時は、少し戸惑いました。(もちろん、無理強いされることなく、PC作業に変更してもらえましたが)
行けなくなったときはどうする?「休所」という選択肢
順調に通えていた時期もありましたが、ある時から、だんだんと事業所へ向かう足が重くなっていきました。
焦りや疲れ、体調の波。
それらが積み重なり、ある朝、ぷつんと糸が切れたように動けなくなってしまったのです。
「頑張れなかった」という挫折感もありました。
でも、「うまくいかない時期があっても大丈夫」。
むしろそれが、自分を守るための大事なステップだったと、今なら思えます。
今あなたが感じている不安や経験も、決して無駄にはなりません。
【併設されていたから分かった】就労移行・継続支援のリアルな雰囲気
私が通っていた事業所は平屋建てで、サービスごとに部屋の扉が分かれているような作りでした。
就労移行支援の部屋
いつも静かで、ピリッとした集中感が漂っていました。
スーツ姿の人が面接練習をしていたり、多くの人がパソコンに向かって資格取得の勉強をしていたり。
「就職」という明確な目標に向かっている、真剣な空気が感じられました。
就労継続支援(A型/B型)の作業室
こちらは、和やかな雰囲気が印象的でした。
特にB型は、スタッフさんと談笑しながら、自分のペースで軽作業に取り組んでいる方が多かったです。
A型はもう少し黙々と作業に集中している感じでしたが、それでも休憩時間は皆さんリラックスして話していました。
【後悔しないために】事業所選びで絶対に確認すべき3つのこと
その経験から学んだ、事業所選びで本当に大切なことを3つお伝えします。
1. プログラム内容より「人」との相性を見極める
どんなに素晴らしいプログラムがあっても、スタッフさんや他の利用している方との相性が合わなければ、通い続けるのは苦痛になります。
見学や体験利用の際には、以下の点をチェックしてみてください。
- スタッフさんは、こちらの話を急かさずに聞いてくれるか
- 利用者さんたちの表情は明るいか、挨拶を交わす雰囲気か
- 施設全体が、自分にとって「居心地が良い」と感じられるか
2. 「休む」ことへの理解度を確認する
うつ病の治療中は、体調に波があって当たり前です。
だからこそ、「休みやすさ」はとても重要。
私の体験からも、これは断言できます。
見学の際に、休む時のルールは正直に聞いてみましょう。
- 体調不良で休みたい時、連絡はいつまでに、どんな方法で必要ですか?
- どのくらい休んでも在籍できますか?(休所制度はありますか?)
休むことに対して、柔軟に対応してくれるかどうかは、安心して通うための生命線です。
3. 見学時に聞くべき「魔法の質問」
事業所のスタンスや柔軟性を知るために、少しだけ勇気を出して、こんな質問をしてみるのがおすすめです。
この質問への答え方で、事業所がどれだけ利用者の体調に寄り添ってくれるかが、透けて見えてきますよ。
【まとめ】焦らなくていい。就労支援は「再出発の準備室」
就労支援は、ただ働くための場所ではなく、自分のペースで社会と再びつながるための練習場です。
通うこと自体が目的になるのではなく、あなた自身が安心して、心と体を休めながら、次の一歩を踏み出すための準備をする。
それが、一番大切なことです。
あなたに合う「止まり木」が、きっと見つかるはずです。
今はまだ、動けなくても大丈夫。
焦らないでくださいね。
今日、この記事を最後まで読めたあなたは、もう、昨日よりちゃんと前に進んでいますから。
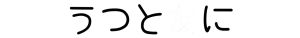
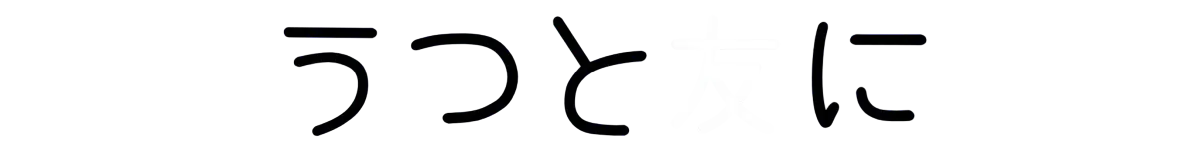
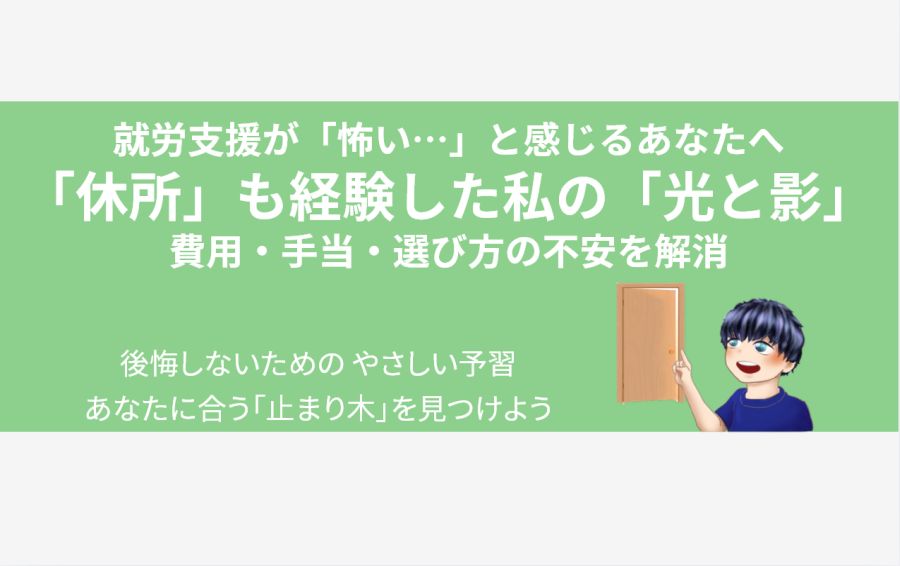

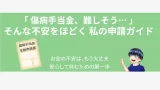
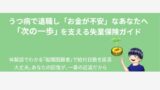

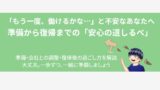

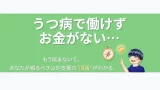
お気軽に感想をどうぞ