「夜は目が冴えて眠れず、朝は泥のように眠くて起きられない」
「昼夜逆転の生活を直したいけど、気合だけではどうにもならない」
「周りから『怠けている』と思われているようでつらい」
そんな悩みを抱え、自分を責めていませんか?
かつての私も、「なぜ自分だけみんなと同じように生活できないんだろう」と、長年ひとりで苦しんでいました。
そのつらい症状、あなたの意志の弱さや気合の問題ではないかもしれません。
私自身が診断された「概日リズム睡眠障害」という、体内時計のリズムが乱れてしまう病気の可能性があるからです。
この記事では、当事者である私が、
- 症状の正体と原因
- 試行錯誤してきた治療法(うまくいかなかった体験も正直にお話しします)
- 日常生活での症状との上手な付き合い方
これらを、自身の体験談を交えて詳しくお話しします。
もしかして…?概日リズム睡眠障害 症状セルフチェック
まずは、あなたに当てはまるものがあるか、チェックしてみてください。
- 希望する時間に眠ったり、起きたりすることが難しい
- 夜になるとかえって頭が冴えてしまい、なかなか寝付けない
- 午前中は頭が働かず、集中力や判断力が低下する
- 無理して早起きしても、日中に強い眠気に襲われる
- 休日になると生活リズムが大きく乱れ、平日に戻すのがつらい
- 遅刻や欠席が多く、社会生活に支障が出ている
※これらの症状が長く続く、または日常生活に支障を感じる場合は、一人で抱え込まず専門の医療機関への相談をおすすめします。
【体験談1】「怠け者」と自分を責め続けた27年間
私が自分の症状に悩み始めたのは、物心ついた頃からでした。
幼稚園のお昼寝の時間には一度も眠れたことがなく、いつも寝たふりをして過ごしていました。
小学生になると、夏休みに入るたびに決まって昼夜が逆転し、新学期が始まる頃に無理やり元に戻す…という生活の繰り返しでした。
高校生になると、その傾向はさらに顕著になります。
夜は目が冴えて眠れないのに、朝は何度アラームをかけても起きられない。
当然のように遅刻は常習犯。親や先生からは「気合が足りない」「自己管理ができていない」と叱られ、自分でも「なんて自分はダメなんだろう」と責める毎日でした。
社会人になってからも状況は変わりません。
大切な会議がある日に寝坊してしまったり、友人との約束をすっぽかしてしまったり…。
そのたびに自己嫌悪に陥り、「普通に朝起きて、夜眠る」という、みんなが当たり前にできることができない自分が嫌でたまりませんでした。
【体験談2】病名がついて、初めて見えた希望の光
心療内科の扉を叩くまで
転機が訪れたのは、27歳でうつ病を発症したことがきっかけです。
うつ病の治療の一環で、毎日つけていた睡眠日誌を主治医に見せたところ、睡眠のリズムに大きな乱れがあることがわかりました。
そして28歳の時、思いがけず「概日リズム睡眠障害」という診断が下されたのです。
「体質です」―医師の言葉に救われた日
診察室でこれまでの経緯を話すと、医師は私の話をじっくりと聞き、こう言いました。
「それは、あなたのせいではありません。生まれつき、睡眠を促すホルモン(メラトニン)を作る力が弱い体質なんです」
その言葉を聞いたとき、涙は出ませんでした。ただ、驚きと戸惑いで頭がいっぱいになりました。
長年、自分の「怠け」や「甘え」だと思い込み、責め続けてきた苦しみの原因が「体質」だったなんて…。
すぐには受け入れられませんでしたが、少しずつ「自分を責めなくてもいいんだ」と思えるようになり、前向きに症状と向き合うきっかけになりました。
「非24時間型」から「睡眠相後退型」へ―診断の揺らぎと現実
最初に医師から告げられた診断名は「非24時間型睡眠覚醒障害」でした。
体内時計の周期が24時間より長いため、睡眠時間が毎日少しずつ後ろへずれていくタイプです。
ただ、私の症状は典型的なパターンに当てはまらなかったようで、主治医が変わってからは「睡眠相後退症候群」と診断が変わりました。
このように、診断名が一つに定まらないほど、症状の現れ方は人それぞれなのだと実感しています。
ちなみに、私が診断された当時は、この症状に効く薬が国内で承認されておらず、医師から「海外からメラトニンのサプリメントを個人輸入してください」と、強く勧められたこともありました。
それほど、この病気との付き合いは長く、手探りの連続だったのです。
そもそも概日リズム睡眠障害とは?体内時計がずれる原因を解説
では、なぜこのような症状が起こるのでしょうか。
その鍵を握るのが、私たちの体にもともと備わっている「体内時計(サーカディアンリズム)」です。
私たちの体に備わる「体内時計」の仕組み
人間の体内時計の周期は、きっかり24時間ではなく、「約25時間」と言われています。
つまり、何もしなければ私たちの生活リズムは、毎日1時間ずつ後ろにずれていってしまうのです。
なぜ体内時計は毎日リセットされるの?
それでも私たちが毎日ほぼ同じ時間に起きられるのは、地球の24時間周期に体内時計を合わせる「リセット機能」が備わっているからです。
このリセットに最も重要なのが「朝の光」です。
朝、太陽の光を浴びると、脳内でセロトニンという物質が分泌されます。このセロトニンは日中の活動を支えるだけでなく、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」に変化し、私たちを自然な眠りへと導いてくれるのです。
体内時計がずれてしまう「内的要因」と「外的要因」
概日リズム睡眠障害は、この体内時計のリセット機能がうまく働かないことで起こります。
その原因は、大きく2つに分けられます。
- 内的要因(体質的なもの)
- 私のように、生まれつきメラトニンを分泌する力が弱いなど、体質的な問題が原因のケース。
- 外的要因(環境や生活習慣)
- シフト勤務や長時間労働、夜間のスマホ操作など、生活習慣や環境が原因で体内時計が乱れるケース。
あなたはどのタイプ?チャートでわかる概日リズム睡眠障害
概日リズム睡眠障害には、症状の現れ方によっていくつかのタイプがあります。
自分はどのパターンに近いか、参考にしてみてください。
- 睡眠相後退型
- 明け方近くまで寝付けず、いったん眠ると昼過ぎまで目が覚めない「極端な夜型」。若者に多く見られます。
- 非24時間型
- 睡眠と覚醒のリズムが毎日1〜2時間ずつ遅れていき、周期的に昼夜逆転を繰り返します。
- 睡眠相前進型
- 夕方頃に眠くなり、深夜や早朝に目が覚めてしまう「極端な朝方」。高齢者に多く見られます。
- 交代勤務型
- 夜勤など不規則な勤務形態により、睡眠リズムが乱れてしまうタイプです。
私の場合は、このチャートだけでは判断が難しく、専門医による詳しい問診が必要でした。
当事者が語る|治療法と症状との上手な付き合い方
治療法は原因や体質によって効果が異なります。
ここでは、私が実際に試した治療法と、正直な感想をお話しします。
STEP1:自分の睡眠リズムを知る「睡眠日誌」
治療の第一歩は、自分の睡眠パターンを正確に把握することです。
何時に寝て、何時に起きたか。日中の眠気はどうか。などを記録する「睡眠日誌」をつけることで、医師も診断や治療方針を立てやすくなります。
STEP2:専門医と行う代表的な治療法
高照度光療法【体験談:効果と断念した理由】
体内時計をリセットするために、朝に強い光を浴びる治療法です。
私は持ち運びが便利な「眼鏡タイプ」を試しました。
朝、装着するだけで家事をしながら光を浴びられるのは手軽で良かったのですが、私には光が眩しすぎたようで、長時間使用すること自体がストレスになってしまい、残念ながら長続きしませんでした。
ただ、この方法で生活リズムが整ったと感じる方が多いのも事実です。
そのため、次は目に負担が少ないと言われる「据え置きタイプ」の購入を検討しています。
薬物療法
体内時計のリズムを整える目的で、メラトニン受容体作動薬(ロゼレムなど)が処方されることがあります。
これは、脳にあるメラトニンが作用する部分を刺激し、自然に近い眠りを促す薬です。
一般的な睡眠薬とは作用の仕方が異なります。
STEP3:自分に合った付き合い方を見つけるために
原因によって、症状との向き合い方も変わってきます。
外的要因の場合
シフト勤務や生活習慣が原因の場合は、働き方を見直したり、寝る前のスマホを控えたりといった環境調整で、症状が改善する可能性があります。
内的要因の場合(私の場合)
私のように体質的な要因が大きい場合、「完治」は難しいかもしれません。
だからこそ、「治す」ことよりも「症状をコントロールしながら、いかに楽に生活するか」という視点が大切だと感じています。
私が今も続けているのは、
- 朝起きたら、まずカーテンを開けて光を浴びる
- 午前中に公園のベンチに座って過ごす
- 朝食をしっかり食べる
といった、基本的なことです。
これらを意識するだけでも、体のだるさが少し和らぐように感じています。
まとめ:あなたの「起きられない」は、決して気合の問題ではありません
この記事の要点を、もう一度振り返ります。
- 「眠れない・起きられない」のは、意志の弱さではなく「体内時計のずれ」が原因かもしれない。
- 原因には体質的なもの(内的)と環境的なもの(外的)がある。
- 治療法は一つではなく、専門医と相談しながら自分に合った付き合い方を見つけることが大切。
かつての私のように、「起きられない」ことで自分を責め、孤独を感じているかもしれません。
でも、あなたは一人ではありません。
その悩みは、決してあなたのせいではないのです。
もしこの記事を読んで、少しでも思い当たることがあれば、どうか一人で抱え込まず、専門の医療機関に相談してみてください。
正しい知識と対策が、あなたの毎日を少しでも楽にしてくれるはずです。
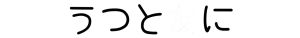
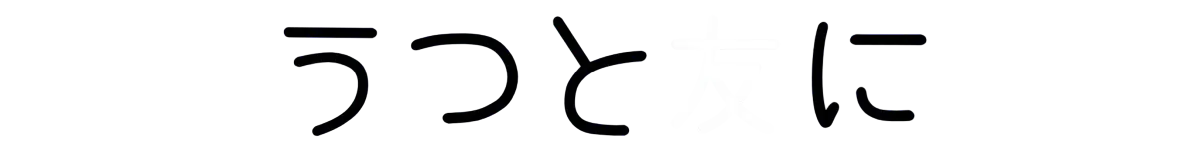
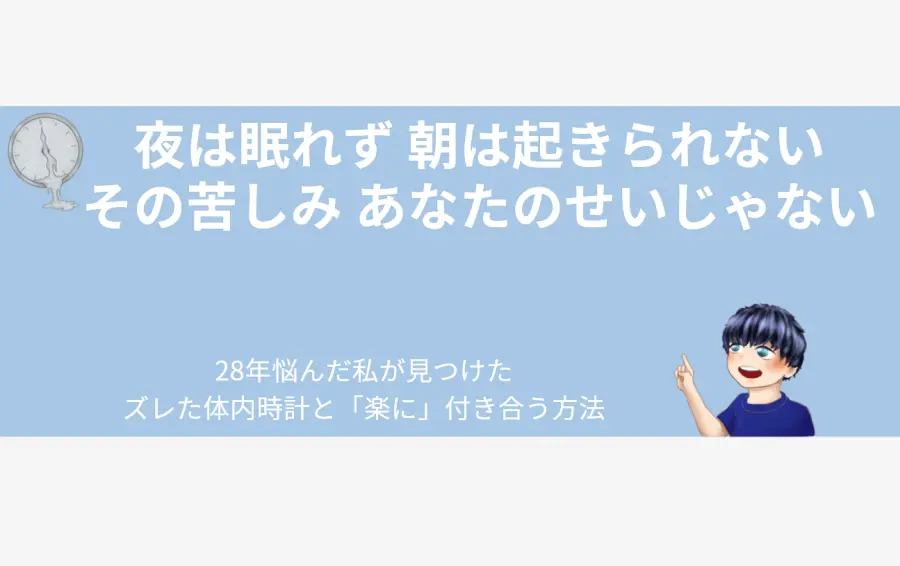
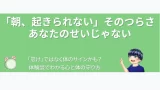
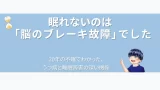
お気軽に感想をどうぞ