ベッドの中で、ついスマホを開いてしまい、友達のキラキラした投稿に心が沈む…。
見たくないのに、気づけば無意識にX(旧Twitter)やInstagramのアプリを開いている…。
かつての私も、そんなSNSとの付き合い方に苦しんでいました。
「見なければいい」と頭ではわかっているのに、やめられない。
そして、そんな自分を責めて、さらに落ち込んでしまう。
もしあなたが今、同じような葛藤を抱えているのなら、この記事はきっとあなたの「お守り」になります。
この記事でお伝えしたいのは、SNSを完全に断ち切るための厳しい方法ではありません。
うつ病で心が疲れているあなたが、これ以上自分を責めずに、SNSと心地よい距離を見つけるための、やさしいヒントです。
この記事で想定しているSNSは、主にXやInstagramですが、TikTokやLINEなど、他のサービスとの付き合い方に悩んでいるあなたにも、きっと役立つはずです。
「SNS疲れ」は、あなたのせいじゃない。うつ病の心にSNSが重くのしかかる4つの理由
まず、一番大切なことをお伝えします。
SNSを見て疲れてしまうのは、あなたの意志が弱いからでも、心が弱いからでもありません。
特に、うつ病で心がエネルギー不足のように感じられるときは、SNSがもたらす刺激はあまりにも強すぎることがあります。
また、スマホが脳に与える影響から、意志の力だけでコントロールするのが難しい場合があると言われています。
「スマホ中毒」という言葉を見聞きしたことがあるかもしれません。
「見たくないのに見てしまう」という葛藤は、あなただけが抱える特別な悩みではないのです。
なぜ、うつ病のときにSNSがこれほどつらく感じてしまうのか。
その理由を知るだけで、少し心が軽くなるはずです。
1. 比較による自己肯定感の低下
SNSは、他人の人生の「ハイライト」だけを切り取って見せる場所です。
楽しそうな旅行、仕事の成功、幸せそうな家族写真…。
それらを見るたびに、無意識のうちに自分の状況と比較してしまい、「それに比べて自分は…」と自己肯定感が削られていきます。

2. 情報過多による脳疲労
タイムラインをスクロールする指は、止まらない。
次から次へと流れてくる膨大な情報は、知らず知らずのうちに、あなたの脳を疲れさせています。
うつ病の症状として、思考力や集中力の低下がみられることがあります。
そんなときに大量の情報が流れ込んでくると、脳がキャパオーバーになり、何も考えられなくなってしまうのです。
3. ネガティブな情報への過剰反応
SNSには、明るいニュースばかりではありません。
攻撃的なコメントや、悲しいニュース、誰かの怒りや不満…。
心のバリエーション機能が弱っているときは、そうしたネガティブな情報に過剰に反応し、他人の感情を自分のことのように受け止めてしまいがちです。
4. 承認欲求と孤独感のループ
「いいね」の数やフォロワーの増減が気になって、何度もスマホをチェックしてしまう。
反応がないと、「自分は誰からも必要とされていないんじゃないか」という孤独感に襲われる。
SNSは、私たちの「誰かに認められたい」という気持ちを刺激しますが、それは時として、心の安定を揺がす諸刃の剣にもなるのです。
ステップ1:情報の洪水から一歩離れる。SNS疲れを軽くする3つの小さな工夫
SNSとの距離を取る、といっても、いきなりアプリを消したり、アカウントを削除したりする必要はありません。
まずは、あなたが浴びる「情報の量」を少しだけ減らすことから始めてみましょう。
一番効果的!まずは通知をオフにしてみる
「ピコン!」という通知音や、画面に表示されるポップアップは、私たちの集中力を奪い、「スマホを見なきゃ」という気持ちにさせます。
まずは、XやInstagramなど、特に疲れを感じるアプリの通知をオフにしてみてください。
これだけでも、無意識にアプリを開く回数がぐっと減り、驚くほど心が穏やかになるのを感じられるはずです。
見たくない情報は「ミュート」でそっと隠す
特定の人の投稿を見ると、いつも心がザワザワしてしまう…。
そんなときは、「ミュート機能」を使いましょう。
相手に知られることなく、その人の投稿を自分のタイムラインに表示させなくすることができます。
フォローを外す罪悪感もなく、人間関係を壊す心配もありません。自分の心を守ることを、最優先にしてあげてください。
「リスト機能」で情報収集と心の交流を分ける
情報収集のためにSNSを使っている人も多いでしょう。
そんなときは、Xの「リスト機能」が便利です。
「信頼できるニュース」や「好きな趣味」など、目的別にリストを作れば、見たい情報だけを効率的にチェックできます。
友達との交流用のタイムラインと、情報収集用のリストを使い分けることで、心の負担を大きく減らすことができます。
ステップ2:自分主導でSNSと付き合う。時間と距離のルール作り
情報の量をコントロールできるようになったら、次は「時間」と「心の距離」を自分で決める練習です。
意志に頼らない!「スクリーンタイム」機能で物理的に制限する
「1日15分だけ」と決めても、ついダラダラと見てしまう…。そんなときは、意志の力に頼るのをやめて、スマホの機能に頼りましょう。
iPhoneなら「スクリーンタイム」、Androidなら「デジタルウェルビーイング」という機能を使えば、アプリの使用時間を設定し、時間になると自動的に利用を制限してくれます。
詳しい設定方法は、「iPhone スクリーンタイム 設定」のように検索すると、お使いのバージョンに合った解説が見つかりますので、ぜひ試してみてください。
「寝る前1時間」と「起きてすぐ」は見ないルール
寝る前のスマホは、ブルーライトの影響で睡眠の質を下げてしまうことがあります。
また、朝起きてすぐにネガティブな情報に触れると、その日一日を憂鬱な気分で過ごすことになりかねません。
「寝る前1時間と、起きてすぐはSNSを見ない」
このルールを守るだけで、睡眠の質が改善し、穏やかな気持ちで一日を始められるようになるかもしれません。
フォロー整理の罪悪感をなくす、やさしい考え方
「この人のフォローを外したら、嫌な気持ちにさせてしまうかも…」
そう考えて、フォロー整理をためらっていませんか?
あなたが誰をフォローするかは、あなたの自由です。
しかし、相手との関係性を考えると、急にフォローを外すことに抵抗を感じるかもしれません。
そんなときは、まずステップ1で紹介した「ミュート」を試してみましょう。
相手との関係は保ったまま、自分のタイムラインを心地よい空間にすることができます。
無理に関係を続ける必要はありません。今のあなたにとって、心穏やかでいられる情報だけを選ぶことを、自分に許してあげましょう。
ステップ3:罪悪感ゼロで「離れる」練習。デジタルデトックスの始め方
もし、ここまでのステップを試しても、まだSNSがつらいと感じるなら。
思い切って、少しだけ「離れる」練習をしてみるのも一つの手です。
一番簡単!アプリをホーム画面から消すだけ
アンインストールするのは勇気がいる、という方は、まずホーム画面からアプリのアイコンを消してみてください。
フォルダの奥深くにしまっておくだけでも、アプリを開くまでの手間が増え、衝動的に見てしまうのを防ぐことができます。
週末だけ「SNS断ち」で心のリセットを
いきなり長期間やめるのは不安かもしれません。
まずは、「土曜の午後だけSNSを見ない」というように、週末だけデジタルデトックスを試してみてはいかがでしょうか。
SNSから離れてみると、今まで見過ごしていた現実世界の小さな発見や、自分の心の声に気づけるかもしれません。
アカウントは消せずに「一時停止」でいつでも戻れる
「アカウントを消したら、もう二度とみんなと繋がれなくなる…」
そんな不安があるなら、アカウントを完全に削除するのではなく、「一時停止」や「利用解除」の機能を使いましょう。
多くのSNSでは、アカウント情報を保持したまま、一時的にお休みすることができます。
「いつでも戻ってこれる」という安心感が、SNSから離れる勇気をくれるはずです。
まとめ:SNSの世界から、少しだけ目をそらしてみよう
ここまで、うつ病でSNSに疲れたあなたが、自分を責めずに心を守るためのヒントを3つのステップでご紹介してきました。
- ステップ1:通知オフやミュートで、浴びる情報の量を減らす
- ステップ2:スクリーンタイム機能や自分ルールで、時間と距離を決める
- ステップ3:アプリを隠したり一時停止したりして、「離れる」練習をする
大切なのは、これらすべてを完璧にやろうとしないことです。
今日は通知をオフにできた。
それだけで、素晴らしい一歩です。
週末に半日だけスマホを触らなかった。
それだけで、あなたの心は少し休めたはずです。
できたことを、たくさん褒めてあげてください。
SNSの外には、穏やかな時間が流れています。
温かいお茶の香り、窓から差し込む光、好きな音楽。
ほんの少しだけSNSの世界から目をそらしてみると、すぐそばにある、やさしい現実に気づけるかもしれません。
あなたの心が、少しでも軽くなることを、心から願っています。
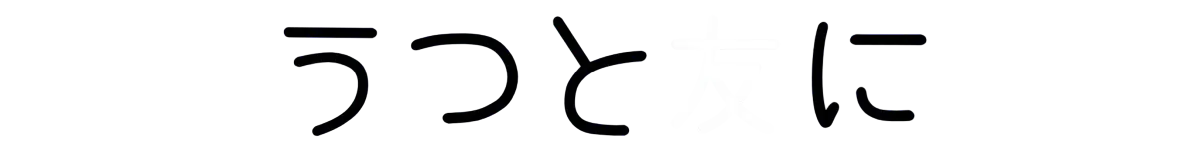
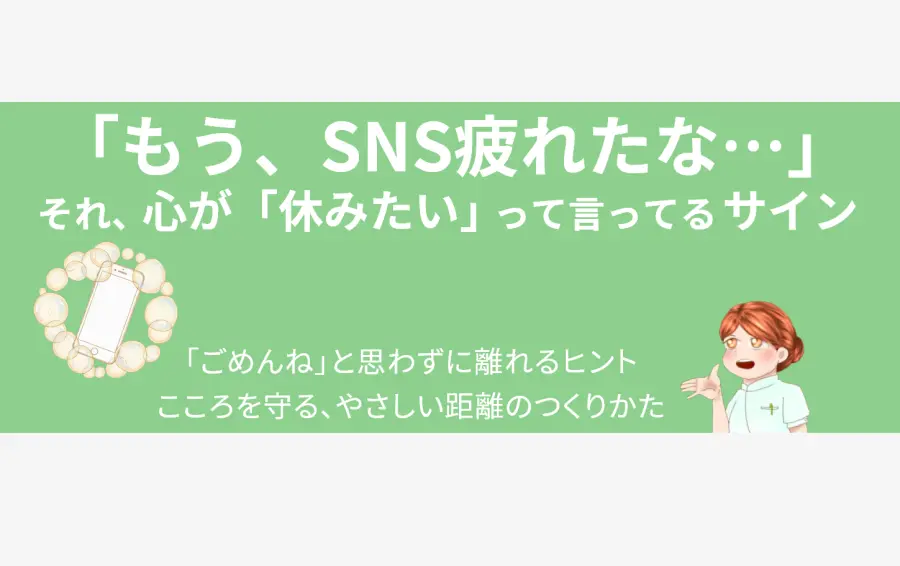

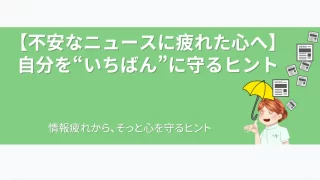

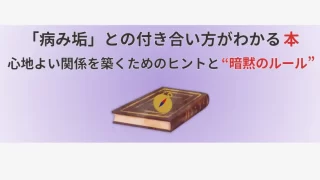
お気軽に感想をどうぞ