鏡に映る自分を見ては、ため息をつく。
SNSで他人の活躍を見ては、心がざわざわする。
眠れない夜には、過去の失敗ばかりが頭をよぎる。
そんな日々を、私は長く過ごしていました。
この記事を読んでくださっているあなたも、もしかしたら、似たような息苦しさを感じているのかもしれませんね。
でも大丈夫。
私自身、自己肯定感との向き合い方を変えたことで、少しずつ心が楽になっていきました。
- 「自己肯定感を高めよう」とすると、なぜか苦しくなる理由
- 無理に高めるのではなく、ありのままの自分を「認める」という考え方
- 今日からできる、心が少し楽になる具体的な3つのステップ

このページでは、うつ病と共に19年以上歩んできた私が、試行錯誤の末にたどり着いた「自己肯定感」との、すこし変わった付き合い方をお話しします。
結論から言うと、ゴールは自己肯定感を無理に「上げること」ではありません。
それは、ありのままの自分を、ただ「認めてあげる」ことです。
この記事が、あなたの心を少しでも軽くする、小さなきっかけになることを願っています。
【体験談】私が自己肯定感を「高める」のをやめて、楽になるまで
「自己肯定感を上げなきゃ」
その思い込みに、私は何年も囚われていました。
自己啓発本を読み漁り、「褒め日記」をつけ、「私はできる!」と自分に言い聞かせる。
巷で良いと言われる方法は、ほとんど試したと思います。
でも、結果はいつも同じでした。
三日坊主で終わっては「やっぱり自分はダメだ」と落ち込み、無理にポジティブな言葉を唱えては、心とのギャップにむなしくなる。
努力すればするほど、理想の自分から遠ざかっていくような感覚でした。
転機が訪れたのは、カウンセリングの中で「自己受容」という考え方に出会ったときです。
カウンセラーの方から「まずは、高められない自分を許してあげませんか」と言われたとき、肩の力がスッと抜けました。
それから私は、「上げる」という目標を、一度ぜんぶ手放しました。
もちろん、すぐに楽になったわけではありません。
でも、一ヶ月ほど経つと、私をガチガチに縛り付けていた「〜しなきゃ」というプレッシャーが、少しずつ消えていることに気づいたのです。
自己肯定感が低い日があってもいい。
弱い自分、ダメな自分も、すべて含めて「私」なんだと。
そう思えたとき、私はようやく、自分自身と和解できた気がしました。
なぜ「自己肯定感を高めよう」とすると、余計に辛くなるのか?
かつての私のように、「高めよう」と頑張るほど苦しくなるのは、なぜでしょうか。
私の経験から、3つの理由をお話しします。
理由1:「今の自分はダメだ」という自己否定から始まっているから
先ほどもお話しした通り、「自己肯定感を上げなければ」という考えは、「今の自分は不完全で、ダメな存在だ」という自己否定が前提になっていることがあります。
こうした考え方のクセは「認知の歪み」とも呼ばれ、自分を不必要に苦しめてしまう原因になることがあります。
ダメな自分を叱って前に進もうとするので、心が疲れてしまうのですね。
理由2:他人との比較がベースにある「プライド」と混同しているから
多くの人が「自己肯定感」と混同しがちなのが「プライド」だと、私は感じています。
本当の自己肯定感が「ありのままの自分」を無条件に大切に思える感覚なのに対し、プライドは「他人より優れている自分」を評価する、相対的なものです。
(もちろん、プライド自体が悪いわけではありません。ただ、他人との比較が苦しさの原因になることもある、ということです。)
他人との比較で自分を測っている限り、心に平穏は訪れにくいのかもしれません。
理由3:そもそも「できなくて当たり前」の環境にいるから
実は、日本人は諸外国と比べて、自己肯定感が低い傾向にあることがデータで示されています。
つまり、あなたが自己肯定感を持てずに苦しんでいるのは、あなた一人のせいではなく、社会や環境の影響も大きいのです。
だから、これ以上「自分のせいだ」と責める必要はありません。
「高める」から「認める」へ。心がスーッと楽になる3つのステップ
では、具体的にどうすれば、ありのままの自分を「認める」ことができるのでしょうか。
ここでは、私が実践して特に効果を感じた、3つの具体的なステップをご紹介します。
誰とも比べず、あなたのペースで試してみてくださいね。
STEP1:評価しない。「今日の事実」を1行だけ書く
まずは感情を横に置き、自分を客観的に見るための土台を作るステップです。
「自分を褒める日記を試したけど、褒めることが思いつかなくて挫折した…」という経験はありませんか?
私もそうでした。「褒めなきゃ」というプレッシャーが、かえって重荷になってしまったのです。
そこで、目的をガラリと変えました。
「褒める」のをやめて、ただ「事実を記録する」ことから始めてみましょう。

- (評価する書き方)→ 今日は散歩に行けてえらかった。でも掃除はダメだった。
- (事実だけを記録する書き方)→ 今日は10分、散歩に行った。掃除はしなかった。
スマホのメモ帳に寝る前に1行書くだけでもいいですし、誰にも見せないSNSの鍵アカウントに投稿するのもおすすめです。
「何もできなかった」と思っていた日でも、記録を見ると「意外と何かしてるな」と気づけたりします。
この小さな気づきの積み重ねが、自分を静かに肯定する土台になるのです。
STEP2:比べない。「SNS」と「過去の自分」から少しだけ離れる
あなたを疲れさせる原因から物理的に距離をとり、心の平穏を取り戻すステップです。
SNSを開けば、きらびやかな他人の日常が目に飛び込んできます。
こうした「SNS疲れ」に心当たりがある方も、少なくないのではないでしょうか。
また、体調に波があるときは、元気だった「過去の自分」と比べて落ち込むこともありますよね。
- 寝る前の15分間は、スマホを機内モードにする
- 見ていて辛くなるアカウントは、そっとミュートする
- 「昨日はできたのに…」と自分を責めそうになったら、「今日は今日。それでいい」と心の中でつぶやく
いきなり「誰とも比べない」を目指すのは、とても難しいことです。
だから、まずは「比べる時間」から少しだけ離れる練習をしてみましょう。
情報から物理的に距離をとることで、心にも穏やかなスペースが生まれてくることがあります。
STEP3:否定しない。どんな感情も「ただ気づいて、名前をつける」
自分の感情を敵とみなすのではなく、ありのまま受け入れる練習をするステップです。
私たちの心には、不安、嫉妬、怒りといったネガティブな感情も浮かびます。
そんな自分を「ダメだ」と責めてしまいがちです。
ここでも、認知行動療法(CBT)の考え方を参考に、自分の感情や思考に「良い/悪い」のレッテルを貼るのをやめてみましょう。
不安な気持ちが湧いてきたら、「不安になっちゃダメだ!」と打ち消すのではなく、「ああ、今、私は『不安』を感じているんだな」と、ただ気づいて、心の中で名前をつけてあげるのです。
どんな感情も、あなたの一部です。
それを無理に追い出そうとせず、ただ「そこにいること」を許可してあげる。
この静かな観察の習慣が、あなたと感情との関係を、より穏やかなものに変えてくれるかもしれません。
まとめ:あなたのペースで、あなたと仲直りしていこう
この記事で最も伝えたかったことは、「自己肯定感は、無理に高めなくてもいい」ということです。
むしろ、自己肯定感が低い自分、弱い自分、ダメな自分…。
そんな、あなたが「変えたい」と願っている部分こそ、切り離すのではなく、優しく受け入れ、認めてあげてほしいのです。
今回ご紹介した3つのステップは、そのための具体的な方法です。
でも、焦る必要はまったくありません。できる日から、できることだけで大丈夫です。
自分自身との関係を再構築するのは、時間がかかる、根気のいる旅のようなもの。
このブログが、その長い旅路の、心強い「友」となれることを、心から願っています。
この記事を書く上で、参考にした本
今回の記事を書くにあたり、臨床心理士の中島輝さんのご著書を参考にさせていただきました。
「自己肯定感」という言葉が、いくつかの感覚(6つの感)から成り立っているという考え方は、私が自分の状態を理解する上で、大きな助けになりました。
もしご興味があれば、手に取ってみてください。
※この記事の内容は、私自身の体験と一般的な心理学の考え方をまとめたものであり、医学的な助言や治療を目的とするものではありません。
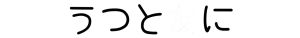
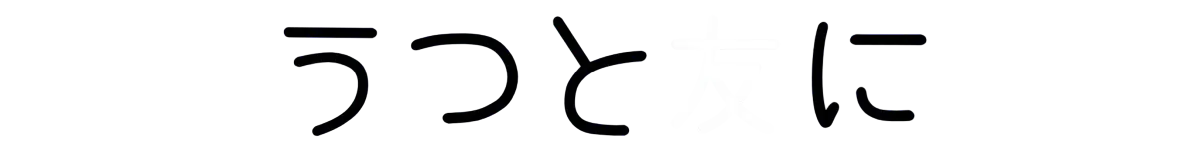
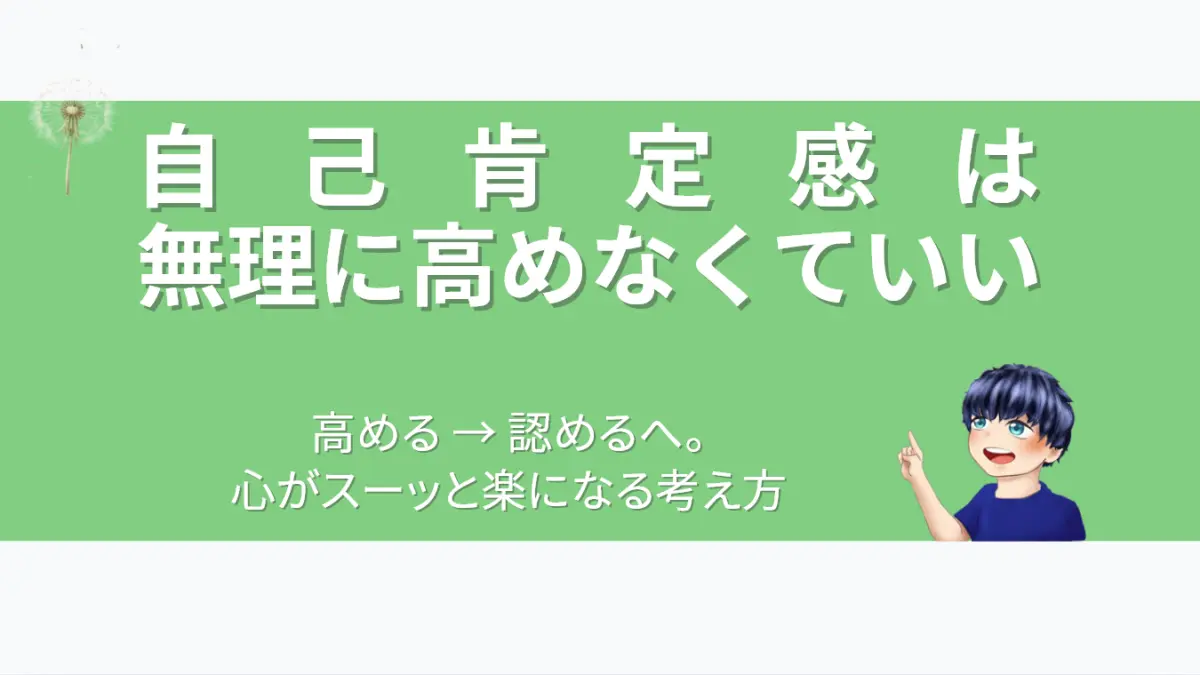

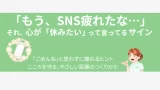
お気軽に感想をどうぞ
Taniです。
おはようございます。
自己肯定感について読ませていただきました。真面目な人は、ともすれば自分に厳しく考えがちだと思います。小さな事から、目標を立ててそれを実施する、そして自分を褒める(肯定する)ことは、大切な事だと思います。
Taniさん、コメントありがとうございます。
記事を読んで頂けて嬉しいです。
私も昔は絵に描いたような生真面目で自分を褒めることが苦手な子供でした。
最近では少しずつ変化が現れて、自分を認められつつあります。
小さなことでもできたことを喜ぶことの大切さに気づけました。