いろいろな想いを乗り越えて、手帳があなたの手元に届いたんですね。
本当にお疲れさまでした。
嬉しい気持ちと同時に、「さて、これから何をすればいいんだろう?」という、少しの不安も感じていませんか。
その手帳は、これからのあなたの暮らしを支えてくれる、心強い「お守り」になります。
この記事では、私が実際に手帳を取得したあと、すぐに行動した5つのステップを、体験談とあわせて具体的にお伝えします。
一つずつ進めていけば、きっと生活の不安が和らぎ、安心につながるはずです。
- 手帳取得後にやるべきことが、具体的なステップでわかる
- 使える制度を見逃さず、生活の負担を軽くするヒントが見つかる
- 一歩踏み出すことで、手帳が「未来を守るお守り」に変わる
精神障害者保健福祉手帳の活用|まずやるべき5つのステップ
手帳を暮らしに活かすために、私がやったことは下の5つです。
「たくさんあって大変そう…」と感じるかもしれませんが、大丈夫。
まずは身近なところから、あなたのペースで一つずつ進めていきましょう。
- 役所の窓口で「使える制度」をまるごと知る
- 毎日の「交通費」と「スマホ代」の負担を軽くする
- 税金の負担を軽くする「障害者控除」の手続きをする
- 未来の「働き方」の選択肢を広げる
- 手帳にまつわる「よくある疑問」を解消する
手帳を取得しようか迷っている段階の方は、まずはこちらの記事から読んでみてください。
【ステップ1】役所の窓口で「精神障害者保健福祉手帳」で使える制度を把握する
まず最初にやるべき、そして最も大切なことは、お住まいの市区町村の役所(障害福祉課など)で、利用できる制度の一覧をもらうことです。
国で一律に決められている制度もあれば、自治体独自の支援もあります。
手帳を受け取ったその足で、窓口の担当者の方に「この手帳で使える制度について教えてください」と尋ねてみましょう。
私の市では、使える制度がまとめられた冊子を渡してくれました。
さらに、担当の方が私の等級(精神3級)で「特に活用できそうなのはこの制度ですよ」と、マーカーを引きながら丁寧に説明してくれたんです。
ネットで調べるだけでは分からない情報も多く、最初にプロに聞けて本当に良かったと感じました。
障害者手帳には「精神」「身体」「療育」の3種類があり、等級によっても受けられるサービスが異なります。
だからこそ、まずは専門家である役所の方に自分の状況に合った情報を教えてもらうのが、一番確実で安心できるスタートです。
【ステップ2】毎日の固定費を見直そう|交通費とスマホ代の負担を軽くする
次に、日々の生活で支出している「固定費」に目を向けてみましょう。
特に交通費やスマホ代は、割引制度を使うことで効果を実感しやすい部分です。
交通機関の割引:よく使う電車やバスから調べてみよう
通院や外出で、電車やバスなどの公共交通機関を使う機会は多いですよね。
精神障害者保健福祉手帳を持っていると、運賃の割引が適用される場合があります。
ただし、割引の条件は交通機関によって細かく異なります。
公式サイトを確認したり、駅の窓口で直接聞いてみるのが確実です。
私は千葉県在住ですが、通院先は東京都内です。
あるバス会社は「都内在住」が割引の条件だったため対象外でしたが、通院でいつも使う別の都営バスは在住条件がなく、運賃が半額になりました。
毎月のことなので、これは本当に助かっています。諦めずに調べてみてよかったです。
私が実際に調べたときの経験は、こちらの記事で詳しく解説しています。
スマホの障害者割引:まずは電話で相談してみよう
もしあなたが大手3キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)のいずれかと契約しているなら、スマホ料金の負担が軽減される可能性があります。
現在の契約プランによってはプラン変更が必要な場合もあるため、まずは各社のコールセンターに電話して「障害者手帳を使った割引について相談したい」と伝えてみましょう。
あなたの契約状況に合わせた最適なプランをシミュレーションしてくれます。
私はドコモを使っていたので、早速電話でシミュレーションをお願いしました。
その結果、毎月の料金負担が軽くなることが分かり、ハーティ割引(障害者割引)に加入しました。
最初の申し込みは店舗で行う必要がありましたが、その後の手続きの多くは電話やオンラインで進められたので、とてもスムーズでした。
私がドコモで申し込んだときの手順は、下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
【ステップ3】精神障害者保健福祉手帳で税金の負担を軽くしよう「障害者控除」
もしあなたが働いていて所得があり、所得税や住民税を納めている場合、「障害者控除」という制度で税金の負担を軽くできる可能性があります。
これは、年末調整や確定申告の際に申請することで適用される制度です。
すぐに手続きが必要なわけではありませんが、「こんな制度があるんだ」と頭の片隅に置いておくだけでも、いざという時に役立ちます。
私も、手帳を取得した翌年の確定申告から障害者控除を申請しています。
最初は難しそうに感じましたが、一度やってみると意外と簡単でした。
家計の負担を少しでも減らせるのは、精神的な安心にもつながります。
障害者控除の詳しい仕組みや申請方法については、こちらの記事が参考になります。
【ステップ4】未来の選択肢を広げよう|安心できる「働き方」を見つける
今はすぐに仕事のことを考えるのが難しいかもしれません。
でも、障害者手帳は、あなたの体調を第一に考えた「働き方」の選択肢を広げてくれる大切なお守りにもなります。
もし将来、転職や就職を考えるときが来たら、「障害者雇用」という働き方を選べるようになります。
これは、障害への理解や配慮がある環境で働くための特別な雇用枠です。
また、すぐに企業で働くのが難しい場合には、「就労移行支援」や「就労継続支援」といった福祉サービスを利用する道もあります。
これらは、体調と相談しながら仕事の訓練をしたり、軽作業を行ったりする場所です。
私も現在、まずは心身の調子を整えることを目的に「自立訓練」という福祉サービス事業所に通っています。
自分のペースで社会とのつながりを持てる場所があるのは、とても心強いです。
こうした選択肢があることを知っているだけで、未来への不安が少し軽くなると思います。
就労支援サービスについては、私が実際に通ったときの体験談をこちらの記事で詳しく解説しています。
【ステップ5】精神障害者保健福祉手帳のよくある疑問を解消する(FAQ)
ここでは、私が実際に相談を受けたり、多くの方が疑問に感じたりしていることについて、Q&A形式でまとめました。
手帳を持つデメリットはないの?
申請や更新の際に診断書をもらう手間や、その費用がかかることくらいです。
一番のハードルは、国から「障害者」と認定されることを受け入れる、ご自身の気持ちの部分かもしれません。
しかし、手帳はあなた自身を守るための大切な支えです。必要がなくなれば、いつでも返納できます。
会社にバレずに使う方法は?
手帳を申請・取得したことが、役所から会社に連絡がいくことは一切ありません。
ただし、会社の年末調整で「障害者控除」を申請すると、経理担当者には手帳の存在が伝わります。
もし会社に知られずに控除を受けたい場合は、年末調整では申請せず、ご自身で確定申告を行うという方法がありますが、ご自身の判断と責任において行ってください。
更新はいつ、どうすればいい?
手帳の有効期限は2年間です。
期限が近づくと役所からお知らせが届くことが多いですが、忘れないように注意しましょう。更新には、再度医師の診断書が必要になります。
ちなみに、自立支援医療の有効期限(1年)と更新タイミングを合わせると、診断書を1通で済ませられる場合があるので、手間や費用を節約できますよ。
もし紛失してしまったら?
万が一なくしてしまったら、まずは警察に紛失届を出しましょう。
その後、お住まいの役所で再交付の手続きを行えば、再発行してもらえます。
再交付には顔写真が必要ですが、診断書は不要です。
ここまでで、手帳を暮らしに活かすための準備が整いましたね。
まとめ:手帳は、あなたの暮らしを守る「お守り」です
今回は、精神障害者保健福祉手帳を取得したあとに私がやった5つのステップをご紹介しました。
- 役所の窓口で「使える制度」をまるごと知る
- 毎日の「交通費」と「スマホ代」の負担を軽くする
- 税金の負担を軽くする「障害者控除」の手続きをする
- 未来の「働き方」の選択肢を広げる
- 手帳にまつわる「よくある疑問」を解消する
障害者手帳を持つことは、ゴールではありません。
それは、あなたが自分らしい生活を守り、安心して毎日を送るためのスタートです。
持っていることで精神的な葛藤を感じることもあるかもしれません。
でも、この手帳があなたの未来の可能性を広げ、いざという時にあなたを守ってくれる「お守り」になる、そんな心強い存在だと私は感じています。
この記事が、あなたの次の一歩をそっと後押しできたら、これほど嬉しいことはありません。
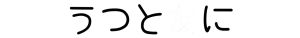
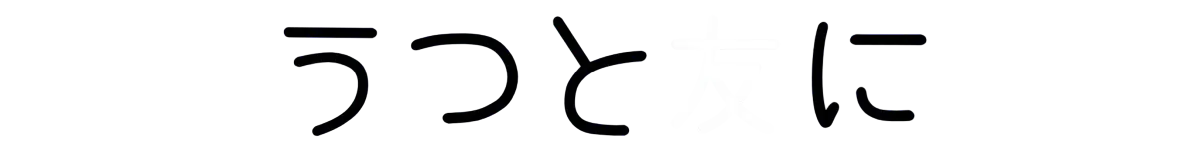
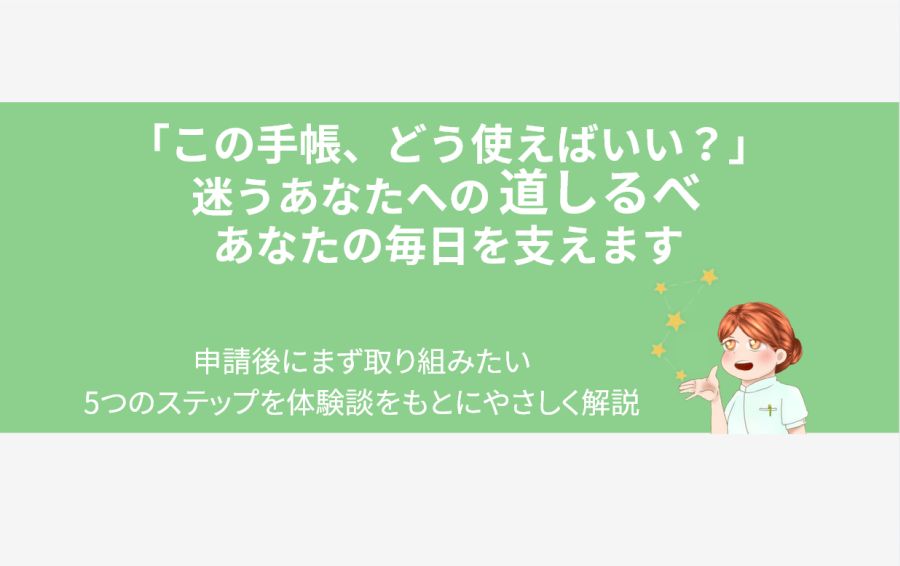




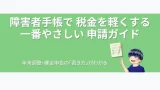

お気軽に感想をどうぞ