うつ病の治療中は、本当に苦しいですよね。
先の見えない不安な気持ち。
思うように動かない心と身体。
まるで、霧の中を一人で歩いているような、心細さ。
そんな中で、ふと頭をよぎる、お金のこと。
「治療費は、これからどうなっていくんだろう…」
「働けない間の生活は、大丈夫かな…」
その心配が、あなたの心をさらに重くしているかもしれませんね。
でも、どうか安心してください。
あなたが今、真っ暗闇だと感じているその場所にも、ちゃんと道は続いています。
今のあなたを支えるための制度は、あなたが思うよりもずっと多く、きちんと用意されているのです。
この記事は、そんなあなたのための、温かい「道しるべ」です。
19年以上にわたり、うつ病と共に生き、様々な制度に助けられてきた私が、この先の道を照らす「お金の羅針盤」として、あなたの状況に合わせて「どの制度が使えるのか」「次に何をすべきか」を、一つひとつ丁寧に、やさしく解説します。
もう、一人で頑張りすぎなくていいんです。
私と一緒に、あなたを守るための大切な知識を、一つずつ確認していきましょうね。
【最初に確認】あなたの状況で使える「お金の支援」がわかるマップ
今のあなたの状況に合わせて、必要な情報がどこにあるかを示した、やさしい地図です。
【まず知っておきたい】生活の土台を支える基本的な制度
ここでは、多くの方が最初に検討する、基本的な制度を紹介します。
自立支援医療制度
うつ病などの精神疾患にかかる医療費の自己負担額を、3割から1割に軽減してくれる制度です。
毎月の通院費やお薬代の負担が、目に見えて軽くなります。
安心して治療を続けるための、心強い制度ですので、多くの方が利用されています。
傷病手当金
うつ病が原因で仕事を休み、会社からお給料が支払われないときに、あなたが加入している健康保険から支給される手当です。
給与のおよそ3分の2が、原則として、最長で1年6ヶ月にわたって支給されることになっています。
(※加入状況によっては例外もあります)
まず、あなたの療養生活をしっかりと支えてくれる、大切な制度です。

【必要に応じて検討したい】あなたの状況に合わせた支援制度
精神障害者保健福祉手帳
税金の負担が軽くなったり(減免)、公共料金や交通機関の割引が受けられたり、様々な経済的メリットを受けられる手帳です。
いわゆる「障害者」と認定されることに、抵抗を感じる方もいるかもしれません。
ですが、これはあなたにレッテルを貼るものではなく、あなたが社会的な支援を受けやすくするための、いわば「パスポート」のようなものだと、私は考えています。
失業給付(雇用保険の基本手当)
会社を退職した後に、次の仕事を見つけるまでの生活を支えるための手当です。
うつ病であっても、主治医から「仕事を探せる状態です」という許可が出れば、受給できる場合があります。
治療に専念すべきか、再就職を目指すのか、焦らず主治医とよく相談することが大切ですよ。
障害年金
うつ病の治療を始めてから一定期間が経過しても症状が改善せず、生活や仕事に大きな支障がある場合に、国から支給される年金です。
傷病手当金の支給が終わった後の生活を支える、とても重要な選択肢の一つとなります。
高額療養費制度
万が一の入院などで、同じ月に支払った医療費の自己負担額が上限を超えた場合に、その超えた分が後から払い戻される制度です。
自立支援医療が「外来」の費用を対象とするのに対し、こちらは「入院」も含む高額な医療費に備えるための大切な知識になります。
このような制度があると知っておくだけで、いざという時の心の負担が少し軽くなりますよね。
生活保護
病気やその他の事情で収入や貯金がほとんどなく、どうしても生活ができない場合に、国が最低限の生活を保障してくれる制度です。
これは、あなたの命と暮らしを守るための、最後の、そして最も大切なセーフティネットです。
もしあなたが本当に追い詰められているなら、ためらわずに、お住まいの地域を管轄する「福祉事務所」の相談窓口を訪ねてみてください。
【社会復帰とその先の未来へ】暮らしと仕事のサポート制度
住宅確保給付金
離職などにより家賃の支払いが困難になり、住む場所を失うおそれのある場合に、自治体から家賃相当額の給付を受けられる、国の制度です。
生活の基盤である「住まい」を守ることは、安心して療養するための第一歩になります。
生活福祉資金貸付制度
低所得世帯や障害者世帯などが、生活を立て直すために一時的にお金を借りることができる、全国共通の公的な貸付制度です。
これは「給付」ではなく「貸付」ですが、金融機関からの借入が難しい場合の、大切な選択肢の一つになります。

障害福祉サービス(就労支援など)
障害者総合支援法に基づき、社会生活を送る上での様々な困難をサポートしてくれる公的なサービスです。
あなたの希望や状態に合わせて、以下のような多様な支援が用意されています。
- 就労移行支援:一般企業への就職を目指すための訓練や準備をサポート
- 就労継続支援(A型・B型):すぐに一般企業で働くのが難しい場合に、働きながら訓練できる場を提供
- 自立訓練:自立した日常生活や社会生活を送るための訓練をサポート
- 就労定着支援:就職後に、長く働き続けられるように職場との間に入ってサポート

自治体独自の割引・減免制度
これまで紹介した全国共通の制度のほかに、お住まいの自治体が独自に行っている支援もあります。
割引や減免だけでなく、「精神障害者福祉手当」などの名称で、お住まいの地域によっては月額数千円程度の手当が支給される場合もあります。
また、精神障害者保健福祉手帳を持っていると、以下のような料金の負担が軽くなるケースが多いです。
- 住民税、軽自動車税
- 水道料金、下水道料金
- その他、公共施設の利用料など
内容は自治体によって大きく異なるため、一度、お住まいの市区町村の役所の窓口で「どんな支援が受けられますか?」と尋ねてみることをお勧めします。
ヘルプマーク
外見からは分かりにくい困難を抱えていることを、周囲にさりげなく伝えるためのマークです。
これを持つことで、例えば満員電車で席を譲ってもらえるきっかけになったり、困っているときに声をかけてもらいやすくなるなど、必要な配慮を得るための一助となることがあります。
日々の生活の安心に繋がる、大切なお守りのような存在です。
【重要】制度を組み合わせる際の注意点(併給調整について)
それは「併給調整」といって、受け取れる金額が調整されたり、そもそも同時に受け取れなかったりするルールがあることです。
知らずに計画を立ててしまうと、後から「思ったように受給できなかった」という事態になりかねません。
ここでは、特に重要な組み合わせについて解説します。
| 制度A | 制度B | 併給可否・調整 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 傷病手当金 | 失業給付 | 不可 | 「働けない人」と「働ける人」が対象のため、目的が相反します。原則として同時受給はできません。 |
| 傷病手当金 | 障害年金 | 調整あり | 両方受給できる場合、傷病手当金の額が調整(減額または支給停止)されます。 |
| 失業給付 | 障害年金 | OK | 目的が異なるため、原則として両方を満額受給できます。 |
| 障害年金 | 老齢年金 | 選択制 | 両方の受給権がある場合、どちらか有利な方を一つ選択して受給します。(一人一年金の原則) |
| 各種制度 | 労災保険 | 労災優先 | うつ病の原因が「業務上」と認定された場合、労災保険が最優先で適用されます。 |
| 各種制度 | 生活保護 | 他制度優先 | 生活保護は最後の手段です。他に利用できる制度をすべて利用した上で、不足する分が支給されます。 |

一人で抱え込まないで:あなたの伴走者となる相談窓口
あなたの病状を一番理解している主治医の先生に「こういう制度を使いたいのですが」と相談することから、全てが始まります。
他にも、お住まいの市区町村の担当窓口(障害福祉課など)や、病院にいる医療ソーシャルワーカーさんは、制度利用のプロです。
あなたの話に丁寧に耳を傾け、一緒に考えてくれる、心強い伴走者になってくれますよ。
おわりに:あなたに伝えたい、たった一つのこと
ここまで、たくさんの制度を紹介してきました。
もしかしたら、情報量の多さに少し疲れてしまったかもしれませんね。
でも、どうか忘れないでください。
これらの知識は、あなたを縛るものではなく、あなた自身を守るための「武器」であり、そして「お守り」です。
これまで、あなたは十分に頑張ってきました。
だから、今は社会の仕組みに少しだけ頼って、心と身体を休めることを、自分に許してあげてください。
支援を受けることは、あなたの正当な権利なのですから。
明けない夜はありません。
この記事が、あなたの心の重荷を少しでも軽くし、明日へ一歩踏み出すための、小さな温かい光になることを、心から願っています。


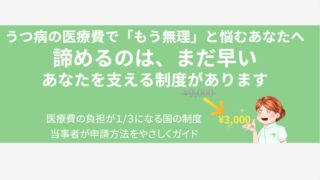
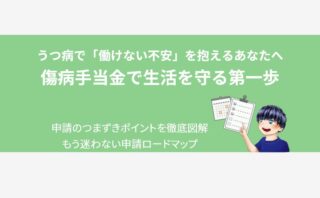
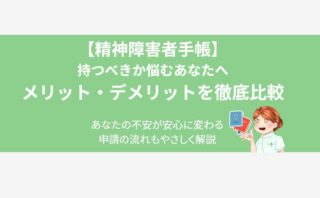
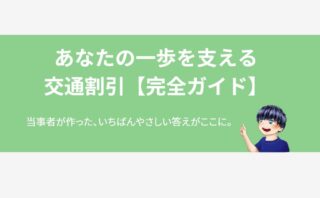
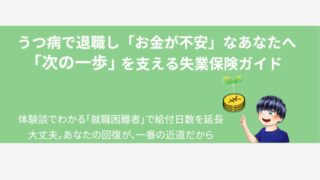
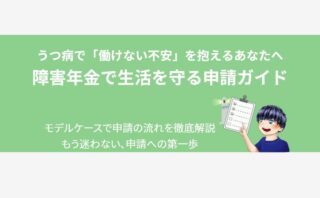
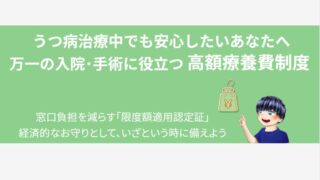
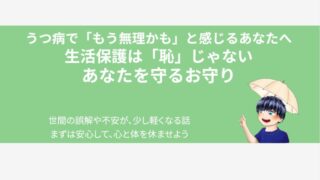
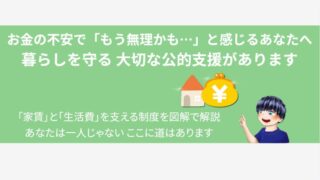
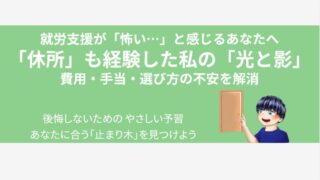
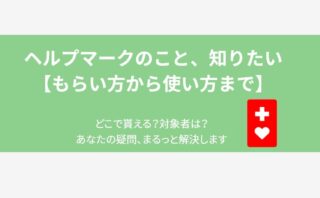
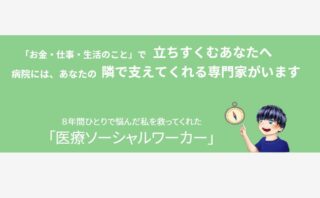
お気軽に感想をどうぞ
精神的に病んでいる時に、お金のことまで考えると余計に病んでしまいそうですね。
でも、こういういろいろな制度を知っておくと心強いし安心できそう(*^^*)
ららぽさん、コメントありがとうございます。
精神的な病気はもちろん、身体的なものも、いつ誰がなるかわかりませんからね。
事前に知っておくだけでも役立つかなって思って調べてみました。
また遊びにきてくださいね&遊びにいきますね♪